Nintendo Switchマリオゲームで子どもと遊ぼう!家族で楽しめるソフトと年齢別の遊び方
Nintendo Switchは、家族みんなで遊べるゲームが豊富なことで知られています。その中でもマリオシリーズのゲームは、子どもから大人まで幅広い年代が一緒に楽しめる定番の「家族向けソフト」です。初めてゲームに触れる初心者のファミリーでも親しみやすく、「マリオゲーム 子どもと遊ぶ」という場面にピッタリの作品が揃っています。

本記事では、Nintendo Switchで遊べるマリオシリーズのゲームについて、未就学児〜小学生の子どもと一緒に家族で楽しむためのポイントをまとめました。各ゲームの基本情報や遊び方、子どもと遊ぶときの難易度やおすすめポイント、さらには年齢別の楽しみ方や家族みんなで盛り上がる工夫まで、マリオゲーム 年齢別の視点を交えて丁寧に解説します。オフライン中心のプレイならではの魅力や、ゲームを通じて育まれる子どもの成長面、家庭内イベントでの活用アイデア、保護者目線でのゲーム選びのポイント、家族の体験談などもご紹介します。
ゲーム未経験のパパ・ママでも安心して読めるよう、やさしくわかりやすい口調でお届けします。Nintendo Switchのマリオゲームを通じて、家族みんなで笑顔になれる時間を作りましょう!
マリオカート8 デラックス
まずは家族向けの鉄板レースゲーム『マリオカート8 デラックス』です。対象年齢はCERO:A(全年齢対象)で、親子で安心して遊べます。Nintendo Switch用ソフトの中でもSwitch 家族向けソフトの代表格であり、小さな子どもから大人まで一緒に盛り上がれる作品です。

基本情報と遊び方
『マリオカート8 デラックス』は最大4人までのオフライン対戦・協力プレイに対応したアクションレースゲームです。マリオシリーズのキャラクターたちがカートに乗り、様々なコースでレースを繰り広げます。操作は直感的で簡単です。アクセルボタンで前進し、ハンドル操作(スティック)で曲がり、アイテムボタンでアイテムを使います。コース上のアイテムボックスから手に入るアイテムを使えば、ライバルを妨害したり、一発逆転を狙えたりするため、ゲームが苦手な子どもでも勝つチャンスがあります。キャラクターやコースの種類も豊富で、飽きずに繰り返し楽しめます。
子どもと遊ぶときの難易度・おすすめポイント
マリオカート8 デラックスは、小さい子どもでも遊びやすい工夫が充実しています。例えば、コースから外れにくくなるハンドルアシスト機能や、自動でアクセルを踏み続けてくれるオートアクセル機能をONにすれば、ゲーム初心者の子どもでも安心です。実際に「5歳の娘はマリオカートのアイテムで相手を逆転するのが大好き」といった声もあり、アイテム要素のおかげで年齢差があっても白熱した勝負ができます。スピードも50cc(低速)から200cc(高速)まで選べるので、初心者の子は低速クラスで練習すると良いでしょう。また、Joy-Conを付属のハンドル型アタッチメントに装着すれば、ハンドルを回すように直感操作ができ、小さな子どもやゲームに不慣れな祖父母でも参加しやすくなります。
年齢別の楽しみ方
- 未就学児: 操作がおぼつかない幼児でも、ハンドルアシストを使えば3~4歳頃からなんとなく走ることを楽しめます。たとえビリになってもカラフルなコースやキャラクターを見ているだけでご機嫌になることも。親が後ろからサポートしつつ、一緒にゴールまで走りきる体験を大切にしましょう。
- 小学校低学年: 5~7歳くらいになると、アイテムの使い所や簡単なドリフト操作も少しずつ理解できるようになります。家族で対戦するときは、時にはチームを組んでレースをしたり、風船バトルなど簡単なルールのモードで遊ぶのもおすすめです。負けても「次は赤こうらを当ててやる!」とリベンジに燃えるなど、勝負の楽しさを学べる時期です。
- 小学校高学年: 8歳以上になると、本格的にテクニックを磨いてタイムアタックに挑戦したり、家族内ランキングを競ったりといった楽しみ方ができます。カートやタイヤの組み合わせを工夫するなど、戦略的に挑む子も増えてきます。大人も本気でプレイすれば子どもたちも真剣になり、家族大会は大盛り上がり間違いなしです。
家族みんなで楽しむ工夫
マリオカートは世代を超えて楽しめるゲームです。兄弟で遊ぶ場合、上の子が下の子に操作を教えてあげたり、「最後はみんなで同時にゴールしよう」と声を掛け合ったりすると微笑ましい協力プレイになります。親子では、親が少し手加減して接戦に持ち込むと、子どもも諦めずにゴールまで頑張れます。祖父母も交えて遊ぶなら、ハンドルアシスト付きでのんびりドライブしたり、「1位になったら○○さん(おばあちゃん)が今日のチャンピオン!」といった家族内表彰を決めると盛り上がるでしょう。短いレース時間の中で何度も勝負できるので、負けてもすぐ「もう一回!」と再戦でき、みんなが熱中できます。
マリオパーティ(スーパー マリオパーティ/マリオパーティ スーパースターズ)
家族や友達とワイワイ遊べるパーティーゲームと言えばマリオパーティシリーズです。Nintendo Switchでは『スーパー マリオパーティ』(2018年)と『マリオパーティ スーパースターズ』(2021年)の2作品が発売されており、どちらも最大4人までのオフラインプレイに対応しています。対象年齢はもちろんCERO:A(全年齢対象)で、小さな子どもでも安心して挑戦できるミニゲームが満載です。
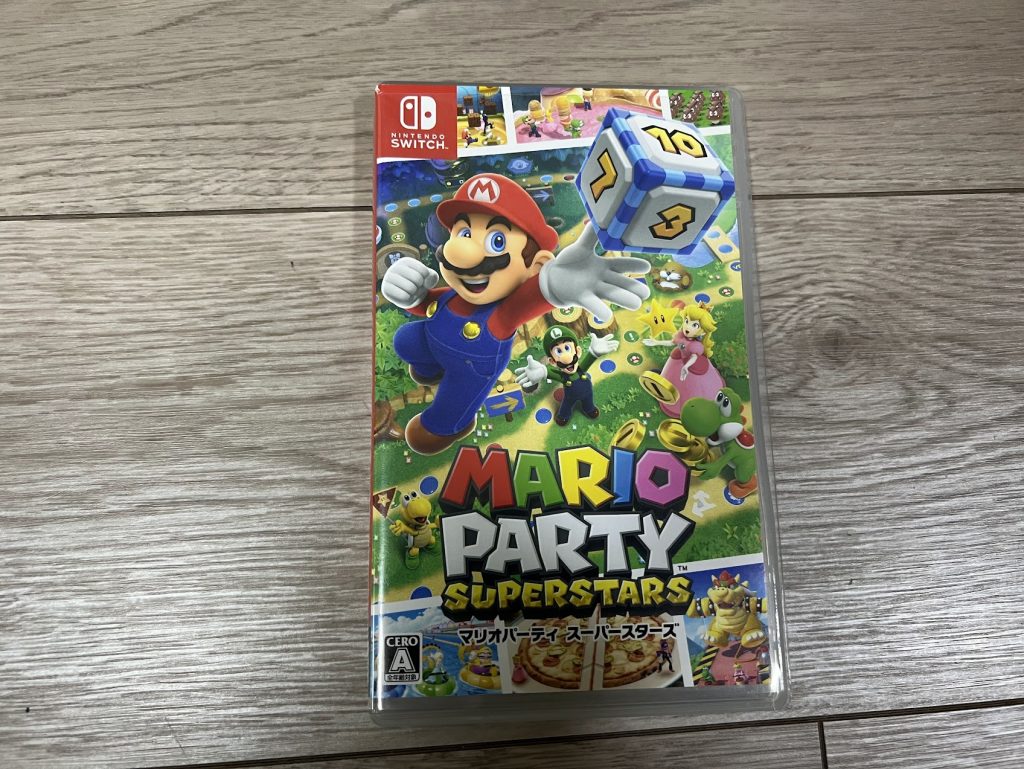
基本情報と遊び方
マリオパーティはボードゲームとミニゲームを組み合わせたパーティーゲームです。プレイヤーはサイコロを振ってボードマップ上を進み、最終的に集めたスターの数を競います。ボード上ではイベントマスによるハプニングがあり、戦略と運の両方が勝敗を左右しますが、ゲームのメインは各所で発生するミニゲームです。ミニゲームは数十種類以上収録されており、ジャンルも操作方法も様々。ボタン1つで遊べる簡単なものから、Joy-Conを振る体感操作のもの、記憶力を試すもの、チーム戦で協力するものまで、多彩なゲームで盛り上がれます。『スーパー マリオパーティ』では特にJoy-Conを活かした体感ミニゲームが多く、4人全員で協力して川下りをする「リバーサバイバル」モードなども搭載されています。『マリオパーティ スーパースターズ』は歴代シリーズの人気ボードとミニゲームを厳選した作品で、操作は全てボタン操作で統一されており、懐かしさも相まって家族みんなで遊びやすい内容です。
子どもと遊ぶときの難易度・おすすめポイント
マリオパーティはルールが比較的シンプルで、幼い子でも参加しやすいゲームです。ただし、スゴロク形式のボードゲーム部分は数の概念や戦略性が必要になるため、未就学児には難しいこともあります。その場合はボードゲームは大人や上の子がリードし、幼児はミニゲームだけを一緒に遊ぶ形でも十分楽しめます。実際、「マリオパーティは3歳の娘にはまだ難しいけど、5歳になったら一緒に全部のモードで遊べた」という家庭もあります。スーパー マリオパーティには2対2で組んで動ける「パートナーパーティ」モードもあり、年齢の近い兄弟でチームを組んで協力すれば、対戦よりも和気あいあいと遊べるでしょう。また、ミニゲームだけを連続して遊べるモードもあるので、飽きっぽい小さな子は好きなミニゲームを選んで短時間で遊ぶのもおすすめです。「4歳の弟が初めてスターを獲得したとき、家族全員で拍手して喜んだ」というエピソードがあるように、誰かが活躍したらみんなで褒めてあげることで、小さな子どもも自信を持って楽しめます。

年齢別の楽しみ方
- 未就学児: 3~4歳ではサイコロを振って進むスゴロクのルール理解は難しいので、大人が付き添いながら一緒にコマを進めてあげると良いでしょう。ミニゲームは簡単なもの(連打するだけ、タイミングよくボタンを押すだけなど)ならチャレンジできます。『スーパー マリオパーティ』のリバーサバイバル(協力川下り)は皆で協力するため、負ける心配が少なく幼児にもおすすめです。できない部分は親が手を添えてサポートし、「上手にできたね!」と成功体験を積ませてあげましょう。
- 小学校低学年: 5~7歳になると、ボードゲームの面白さも少しずつ分かってきます。自分でサイコロの出目を考えて「次は3以上出せばスターが取れる!」などと戦略を立てる子もいます。ミニゲームも種類によって得意不得意が出てくるので、兄弟間で「このゲームはお兄ちゃんに任せて!」など役割分担してチーム戦に挑むのも良いでしょう。負けたときは悔しがるかもしれませんが、それも良い経験。「次はどうしたら勝てるかな?」と一緒に考えてあげると、子どものチャレンジ精神を育めます。
- 小学校高学年: 8歳以上では、大人顔負けの戦略でスターを狙ったり、駆け引きを楽しんだりできるようになります。長期戦のボードゲームでも集中力が続くので、20ターン以上の本格的なマリオパーティ対決も盛り上がります。家族みんなの実力が拮抗してくると、最後のスターの奪い合いはハラハラドキドキ。負けても「もう一回リベンジだ!」と何度でも盛り上がれるのがこの年代です。時には親が本気で勝ってしまうこともありますが、子どもたちは大人相手に勝負できること自体が嬉しく、終わった後は健闘を称え合うなどスポーツマンシップも育っていきます。
家族みんなで楽しむ工夫
マリオパーティはまさにパーティーゲームなので、家族みんなで楽しめる工夫がたくさんできます。例えば、誕生日やクリスマスなど家族イベントの日に「マリオパーティ大会」を開くのも定番です。優勝者にはちょっとしたご褒美(手作りメダルや好きなお菓子など)を用意しておくと子どもたちのやる気もアップします。年齢がバラバラな場合は、あえてチーム戦で大人と子どもをペアにして対戦すると、助け合いながら遊べて一体感が生まれます。祖父母を交える場合は、ボタン1つで遊べるミニゲームや運要素の強いゲームを選ぶとよいでしょう。運任せの展開で思わぬ大逆転が起こり、みんなで大笑いする場面も!ゲーム中は積極的に声を出して応援したり、「次は頑張って!」と声掛けしたりすることで、リビングがまるで運動会のような熱気に包まれます。
マリオテニス エース
スポーツゲームで体を動かしながら遊びたい家族には『マリオテニス エース』もおすすめです。対象年齢はCERO:A(全年齢対象)。マリオシリーズのキャラクターたちと本格的なテニス対戦が楽しめる作品で、1~4人のオフラインプレイに対応しています。
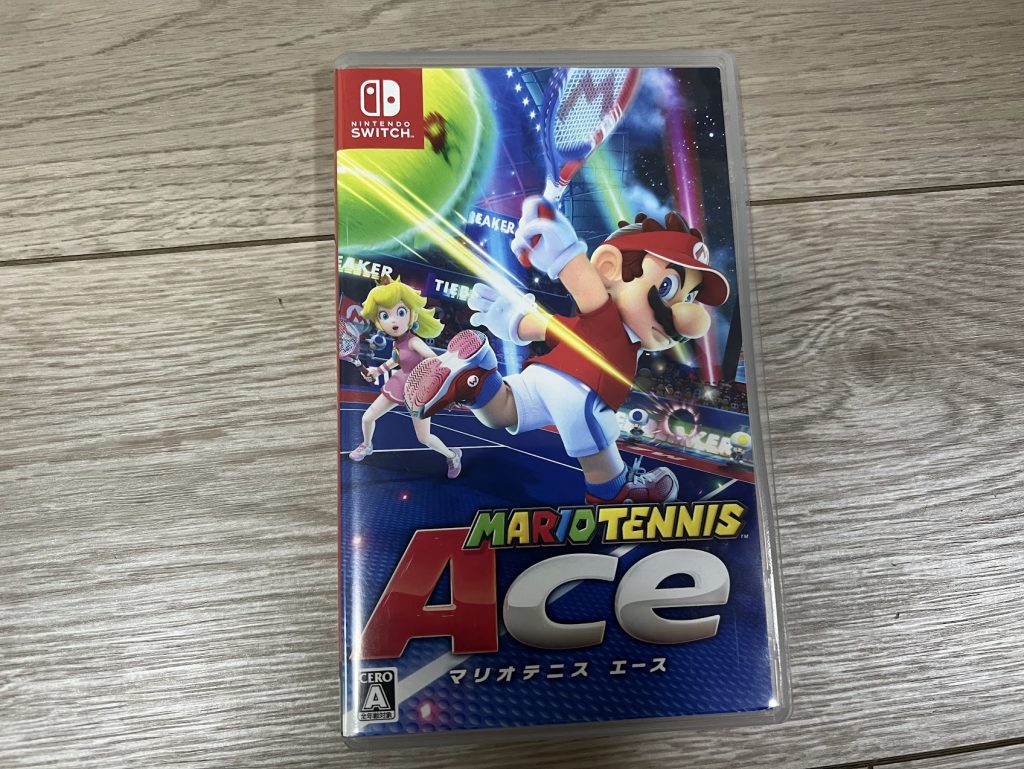
基本情報と遊び方
マリオテニス エースは、マリオたちがテニスで対決するスポーツゲームです。操作キャラクターを左右に動かし、ボタンでショット(球打ち)を放って相手コートにボールを返します。ルールは基本的にテニスそのもので、相手がボールを返せなければポイントです。特徴的なのは、マリオならではのスペシャルショットや作戦が楽しめること。試合中にエネルギーを溜めて放つ強力な「スペシャルショット」や、スローモーションの「ゾーンショット」など、派手な技で盛り上がります。一方で、ゲームに不慣れな人向けにシンプルモード(特殊ショットなしの普通のテニス)も用意されているので、初心者でもルールを覚えやすくなっています。また、Joy-Conをラケットのように振って遊ぶスイングモードでは、画面の指示に合わせて実際にスイングする直感操作が可能です。まるでWiiスポーツのように体を動かしてプレイできるので、家族でワイワイ運動感覚で楽しむことができます。
子どもと遊ぶときの難易度・おすすめポイント
マリオテニス エースは、テニスのルールを理解していれば誰でも楽しめますが、小さな子どもにはサーブや得点の概念が少し難しいかもしれません。その場合はスイングモードで自由にラケットを振らせてあげましょう。ラケットを振るだけでボールを打ち返せるので、4歳・5歳でも笑顔で体を動かしながら参加できます。「小学1年生の娘はJoy-Conを振り回しておじいちゃんとダブルスを楽しんでいます」という声もあるほど、世代を超えて盛り上がれるのがスイングモードの魅力です。標準のスタンダードモード(特殊ショットあり)は駆け引きが複雑になるため、子どもには難しい場合がありますが、シンプルモードに切り替えれば基本的なショットだけのシンプルな試合になります。5歳くらいのお子さんならシンプルモードで十分対戦を楽しめるでしょう。また、ダブルス(2対2の試合)にすれば、親子ペア vs 親子ペアといったチーム戦で協力プレイが可能です。子どもがミスしてもフォローし合えるので、「ナイストライ!」と声を掛け合いながら楽しくプレイできます。
年齢別の楽しみ方
- 未就学児: ルールの細かい理解は難しいですが、スイングモードでボールを打つ動作自体は楽しめます。得点の計算は大人がしてあげて、「いっぱいボールを打ててすごいね!」とプレイそのものを褒めてあげましょう。試合形式にこだわらず、ラリーが何回続くかチャレンジするなどゲーム性を工夫すると、飽きずに遊べます。
- 小学校低学年: この頃になると、サーブからラリー、ポイントまで試合の流れが分かってきます。兄弟でシングルス対決をしたり、親子でダブルスを組んだりと、色々な組み合わせで遊んでみましょう。簡単な作戦(「前衛と後衛に分かれよう」など)も理解できるので、チーム内で相談して動くなど協調性も育ちます。負けて悔しがるときは、「じゃあ次はパパとペアを組んでリベンジだ!」というように味方になって再チャレンジするのも一案です。
- 小学校高学年: テニス経験がなくても、高学年になれば特殊ショットを駆使した戦略的な対戦も楽しめます。ボールの軌道を読んで走る反射神経や、相手のエネルギー残量を見てスペシャルショットを打つタイミングを計る駆け引きなど、大人顔負けの白熱した試合になることもあります。家族でトーナメント戦を開催し、自分たちで優勝トロフィーを作って表彰するイベントにすれば、より一層やる気が高まり思い出にも残るでしょう。
家族みんなで楽しむ工夫
マリオテニスで家族全員が楽しむコツは、「勝ち負け以上にプレイそのものを楽しむ」雰囲気作りです。例えば、良いラリーが続いたら途中でも「ナイスプレー!」とみんなで拍手したり、おもしろい空振りが出たら大笑いしたり、勝敗以外の部分でも盛り上がりポイントを作りましょう。体を動かすスイングモードは、プレイヤーだけでなく見ている家族も思わず体が動いてしまうほど臨場感があります。交代しながら全員で運動不足解消にもなりますし、試合後は「いい汗かいたね!」と爽やかな一体感が生まれます。また、実際のテニスさながらにユニフォームをイメージした服装にしてみたり(赤い帽子をかぶればマリオ気分?)、応援席を作ってぬいぐるみを観客に見立てたりと、小道具や演出を工夫してみるのも子どもは喜びます。
ペーパーマリオ オリガミキング
ユニークな紙の世界を冒険するRPGタイプのゲームが『ペーパーマリオ オリガミキング』です。マリオシリーズの中では物語性が強く、1人プレイ専用ですが、親子でストーリーを楽しんだり謎解きを協力したりするのに適しています。対象年齢はCERO:A(全年齢対象)ですが、テキストの読み応えやパズル要素があるため、小学生以上か大人と一緒のプレイが推奨されるゲームです。
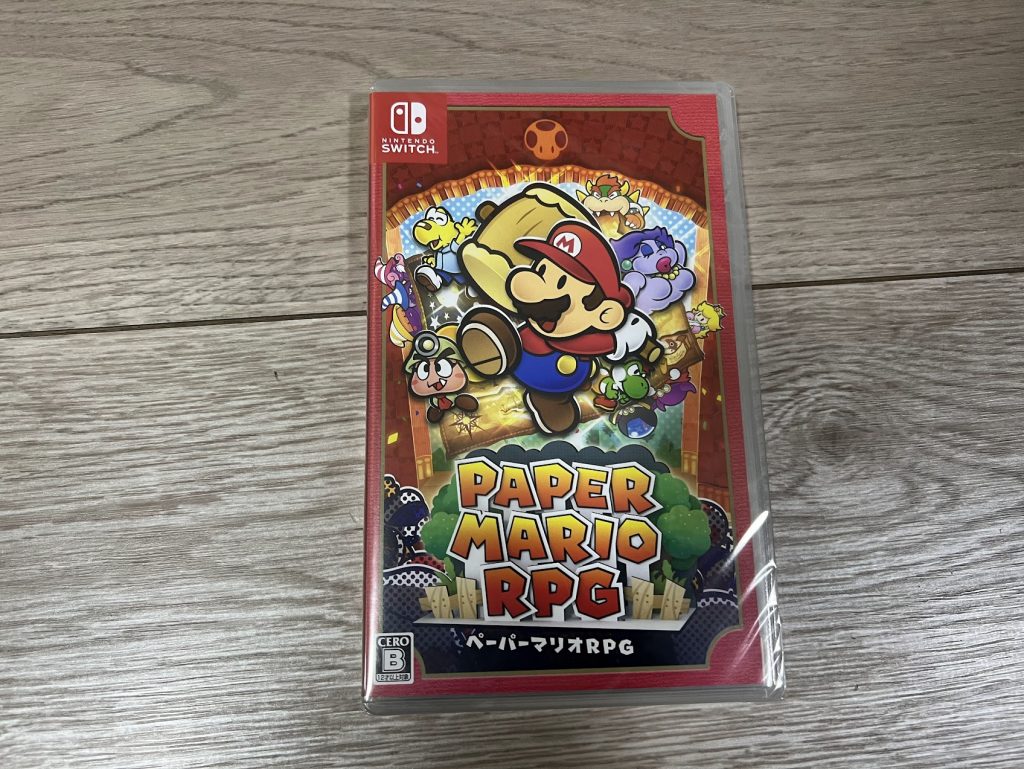
基本情報と遊び方
ペーパーマリオ オリガミキングは、紙のようにペラペラなマリオが活躍する冒険RPGです。オリガミ化してしまった世界を元に戻すため、マリオと相棒のオリビアが各地を冒険します。フィールド上ではさまざまなキャラクターとの会話や謎解きがあり、紙ならではの仕掛け(破れた紙を直す、折り紙の敵を倒すなど)が魅力です。戦闘は一風変わっていて、リング状のパズルになっています。敵が円盤状のマスに配置されており、制限時間内にリングを回転・スライドさせて敵を整列させることで効率よく攻撃できます。このパズル要素は頭を使いますが、難しい場合はヒント機能や仲間キャラのサポートもあるので安心です。ゲーム全体を通してコミカルな会話や演出が多く、大人もクスッと笑えるユーモアが随所に散りばめられています。
子どもと遊ぶときの難易度・おすすめポイント
ペーパーマリオはRPGということもあり、文章の読み取りや謎解き思考が求められます。低年齢の子どもだけで遊ぶには少し難しい場面もありますが、親子で一緒にプレイすることで「考える遊び」として大いに役立ちます。例えば、5歳のお子さんでは戦闘のリング操作が分からず「お母さん助けて!」となるかもしれませんが、それを機に親子で「ああでもないこうでもない」と頭をひねる時間が生まれます。実際に「5歳の娘と一緒にプレイしています。娘はひらがなを読む練習になり、私は謎解きを手伝って親子で達成感を味わっています」という声もあります。ストーリーが進むにつれて明らかになる謎や感動的なシーンもあり、物語を共有する楽しさを子どもに感じさせる絶好の機会です。また、ペーパーマリオはグラフィックが絵本のように可愛らしく、敵キャラも怖すぎないので、ゲーム内容に引き込まれていきます。文字が読めない子には、ぜひ親が読み聞かせをしてあげてください。まるで一緒に絵本を読んでいるかのように、ゲームの世界観を共有できます。難しいパズルを親子で解けたときには「やったね!」とハイタッチすれば、達成感も二人分です。
年齢別の楽しみ方
- 未就学児: 基本的に未就学児が一人でクリアするのは難しいですが、親が操作して子どもが横で見る「観戦プレイ」でも十分楽しめます。むしろ子どもにとっては、大人がプレイするのを見ながら自由にコメントしたり、「あっちに行ってみて!」とお願いしたりするのが楽しいものです。親は子どものリクエストに応えてあげたり、時折「これどう思う?」と選択肢を一緒に考えたりして、参加感を持たせてあげましょう。紙のキャラクターが織りなすコミカルな動きに、きっと笑顔を見せてくれるはずです。
- 小学校低学年: 6~8歳くらいになると、簡単な漢字交じりの文章も読めるようになり、自分で操作する意欲も出てきます。戦闘のパズルは難しいところだけ大人がアドバイスしつつ、基本は子どもの判断に任せてみると良い経験になります。失敗してもゲームオーバーにはなりにくい設計なので、「次はどうする?」と一緒に考えてリトライすればOKです。ストーリーを読み進める中で、推理力や集中力も養われます。親子で「この先どうなるんだろうね?」と予想しながら進めれば、まるで連続ドラマを共有しているようなワクワク感を味わえます。
- 小学校高学年: 9~12歳になれば、もう自力で最後までゲームを進められる子もいるでしょう。ただ、物語の奥深さやギャグのセンスなどは大人が感心する部分も多いので、できれば一緒にプレイしてその感想を語り合ってみてください。例えば、「あのキャラ面白かったね」「この場面ちょっと泣けちゃったね」などと話すことで、ゲーム体験が親子のコミュニケーションになります。高学年の子にとっては、自分の考えや感想を親に聞いてもらえるのは嬉しいものです。エンディングまで見届けたら、ぜひ「よく頑張ってクリアしたね!」と大いに称えてあげましょう。
家族みんなで楽しむ工夫
ペーパーマリオは基本一人用ですが、家族みんなで楽しむには「見守り参加型」の工夫がおすすめです。例えば、夜のリビングで家族が代わる代わる画面を覗き込みながら「あ!そこにヒントがあるよ」「隠し通路を見つけた!」といった具合に、まるでリアルな冒険をみんなでしているような雰囲気を作ると盛り上がります。兄弟がいる場合、操作係とナビゲーター役を交代させてみるのも良いでしょう。片方が操作中、もう片方がお助けキャラのヒント台詞を読んであげたりするだけで「自分も手伝っている」感覚が生まれます。家族で謎解きに詰まったときは、ゲームを一時停止してみんなで「うーん」と考える時間もまた楽しいものです。ちょっとした発想転換で子どもがひらめきを見せたら、「すごい!よく気づいたね」としっかり褒めてあげてください。ゲームクリア後は、物語にちなんだ折り紙工作をしてみるのも面白いアイデアです(オリビアの折り紙人形を一緒に折ってみる等)。ゲームの世界がそのまま創作遊びにも繋がり、子どもの想像力をさらに広げてくれるでしょう。
スーパーマリオブラザーズ ワンダー
2023年に発売された最新の2Dマリオアクション、『スーパーマリオブラザーズ ワンダー』も家族向けに見逃せないタイトルです。対象年齢はCERO:A(全年齢対象)。マリオシリーズ初心者のファミリーにもおすすめできる、新鮮な驚きに満ちた作品となっています。最大4人までのおすそわけプレイに対応しており、家族みんなで同時にコースを冒険できるのが魅力です。
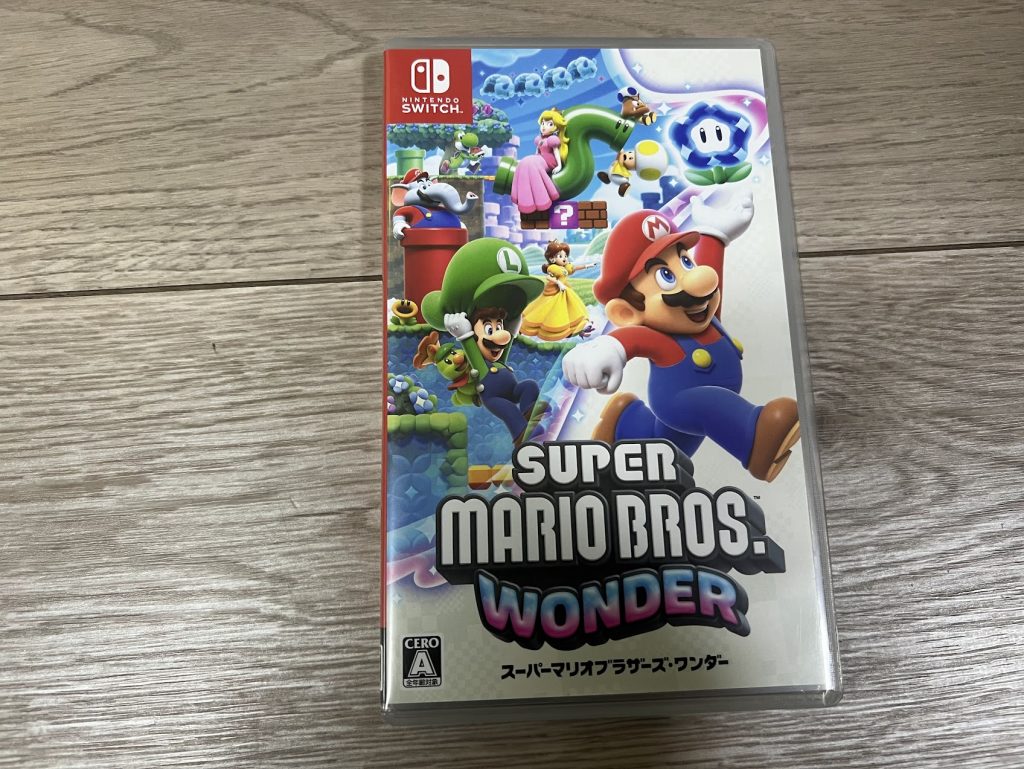
基本情報と遊び方
スーパーマリオブラザーズ ワンダーは、横スクロールで進む伝統的な2Dマリオの最新作です。基本の操作(ジャンプやダッシュなど)は歴代シリーズと同様でシンプルですが、本作ならではの新要素としてワンダーフラワーによる不思議な仕掛けが各コースに存在します。ワンダーフラワーを取ると突然地形が動き出したり、マリオたちの姿が変化したり、とにかく「何が起こるかわからない!」ドキドキの演出が楽しめます。子どもたちはこのサプライズに大喜び間違いなしです。また、新パワーアップとして象に変身する「ゾウマリオ」などユニークな姿になれるアイテムも登場し、見た目のおもしろさも抜群です。プレイヤーキャラクターにはマリオやルイージ、ピーチやデイジーに加えてヨッシーやネコマリオなどが選べ、家族それぞれ好きなキャラでプレイできるのも嬉しいポイントです。コース選択はマップ上で自由度が高く、難しそうなステージは後回しにするなど各自のペースで進められる設計になっています。
子どもと遊ぶときの難易度・おすすめポイント
ワンダーは「驚き」がテーマなだけあり、プレイヤーの年齢に関係なく新鮮な体験を提供してくれます。難易度調整も工夫されており、例えばヨッシーなど一部キャラクターは敵からダメージを受けない設定になっているため、小さい子どもが操作キャラにヨッシーを選べばゲームオーバーになりにくく安心です(穴に落ちるとミスになりますが、仲間が助けるチャンスがあります)。また、4人同時プレイ時にはライフが共有制になっており、一人がミスしても他のプレイヤーが助けてあげればライフを失わずに復帰できます。この協力救出システムのおかげで、上手な人がフォローすれば小さな子でも先に進みやすくなっています。ある家族では「ゲーム初心者の母と5歳児がヨッシーで参加し、ゲーム慣れした父と兄がマリオとルイージでサポートしながら全コースクリアできた」というエピソードもあります。ワンダーフラワーの効果でみんながビックリするような展開になるたびに、家族全員で「すごい!」「何これ!」と盛り上がること請け合いです。加えて、各コースで入手できるバッジというアイテムを装備すると、二段ジャンプやゆっくり落下など特殊な能力が使えます。上手く活用すれば苦手な子も先に進みやすくなるので、家族で「このバッジ付けてみようか」と相談しながら工夫すると良いでしょう。
年齢別の楽しみ方
- 未就学児: 4~5歳でもヨッシーや無敵キャラを使えば、他の人と一緒に画面内を動き回ることができます。難しい操作は不要なので、「ヨッシーに乗ってついていくだけ」でもOK。きれいなグラフィックと不思議な仕掛けにリアクションするだけでも十分遊んでいる気分になれます。もし操作がおぼつかなくても、他のプレイヤーがその子のキャラを抱っこしたり押したりしてあげられるので、安心して冒険について行けます。「自分もみんなと一緒にゴールできた!」という体験が子どもの自信に繋がるでしょう。
- 小学校低学年: 6~8歳ならマリオの操作にも慣れてきて、自分で敵を踏んで倒したりアイテムを駆使したりできるようになります。同時プレイでは「誰が一番コインを集められるか競争ね!」などミニ目標を決めて遊ぶと盛り上がります。ワンダーフラワーの演出に驚いた後、「今のすごかったね!」と感想を言い合ったり、「次はどんな変化が起きるか予想しよう」と話したり、想像力も働かせて楽しめます。時には難しいステージで皆が次々ミスしてしまうこともありますが、そんなときは笑って「どんまい!」と声を掛け合うことで、負けても雰囲気は和やか。ゲームを通じて前向きな声掛けやチャレンジ精神を学ぶ時期です。
- 小学校高学年: 9~12歳になると、隠しコースや高難度チャレンジにも積極的に挑戦したがります。家族で遊んでいて簡単すぎると感じたら、あえて難しいバッジ(例えば操作が難しくなるが得点アップするもの等)を装備してみるなど、自分なりの縛りプレイで盛り上がる子もいるでしょう。また、高学年ともなると下の兄弟の面倒を見る余裕も出てきます。弟や妹がピンチのときに率先して助けに行ったり、「ここは任せて!」とサポート役に回ったりする姿も見られるかもしれません。そのような場面では親としてもしっかり褒めてあげて、兄姉の頼もしさを認めてあげると、ゲーム体験がそのまま上の子の自信や責任感の成長に繋がります。
家族みんなで楽しむ工夫
スーパーマリオブラザーズ ワンダーは4人まで一緒に遊べるので、家族でプレイするときはぜひ全員で同時プレイにチャレンジしてみましょう。最初は画面内がゴチャゴチャして戸惑うかもしれませんが、慣れてくると「○○ちゃんは上のコイン取って!」「パパは敵を倒す係ね!」など自然と役割分担が生まれてきます。また、キャラクターごとに帽子や服の色が違うので、家族で自分の色を決めておくと見失いにくくなります(「今日はママはピーチのピンク担当ね」のように)。テレビモードで遊ぶ場合、大画面に4人分の歓声や笑い声が響いてまさにリビングがテーマパーク状態!テーブルモードで旅行先や帰省先にSwitchを持ち込んで遊べば、親戚の集まりでも即席ゲーム大会が始まります。さらに、本作はスクリーンショット映えするシーンが多いので、プレイ中に面白い瞬間があれば記念に撮影しておくのも思い出になります。後からアルバムを見返して「あのときこんなことで笑ったね」と振り返るのも、家族の絆を感じられるひとときとなるでしょう。
New スーパーマリオブラザーズ U デラックス
初めて家族で楽しむ2Dマリオとして根強い人気を持つのが『New スーパーマリオブラザーズ U デラックス』です。元はWii Uで発売されたタイトルのリメイクですが、Switch版では初心者や子ども向けの新キャラクターが追加されており、まさにマリオシリーズ 初心者 ファミリーにうってつけの作品となっています。対象年齢はCERO:A(全年齢対象)。最大4人までのオフライン協力・対戦プレイが可能です。

基本情報と遊び方
New スーパーマリオブラザーズ U デラックス(以下マリオUデラックス)は横スクロールアクションゲームで、マリオたちがおなじみのクッパに占領されたピーチ城を目指して冒険するストーリーです。操作はジャンプとダッシュが基本で非常にシンプルですが、コース数はなんと合計164もあり(マリオUと追加コンテンツのルイージUを収録)、ボリュームたっぷりです。Switch1台でJoy-Conのおすそわけプレイにより4人同時に遊べます。**マリオUデラックスには小さな子供向けの工夫がたくさん!**最大の特徴は5人のプレイアブルキャラクターが選べる点で、その中の「トッテン(英名: Nabbit)」と「キノピコ(Toadette)」が初心者支援キャラとなっています。トッテンは敵にぶつかってもダメージを受けない特殊能力を持ち、ステージ上の敵をすり抜けて進めます(ただし穴に落ちるとミスになります)。キノピコは専用アイテムのスーパークラウンを取ると「キノピーチ」というピーチ姫そっくりの姿に変身でき、ふんわり滞空ジャンプや一度だけ落下しても自動復帰できる能力を持ちます。これらのキャラを使えば、ジャンプが苦手な子どもでもミスしにくく仲間のサポートもしやすい設計です。
子どもと遊ぶときの難易度・おすすめポイント
2Dマリオは簡単そうに見えて実はアクションゲーム初心者には難しい側面もあります。マリオUデラックスでも、何も補助がなければ小さな子にとっては穴に落ちてばかり…ということになりがちです。しかし、このゲームでは前述のトッテン(無敵キャラ)やキノピコ(救済能力持ちキャラ)のおかげで、未熟な子どもやゲームが苦手なママ・パパでも最後まで遊びやすくなっています。例えば、ゲーム初挑戦だった4歳のお子さんを持つ家庭では、最初はうまく操作できずお父さんのあとを常に「バブル(泡)」で追いかける形だったそうですが、何度かプレイするうちにだんだん上達して自力でゴールできるコースが増えていったそうです。実際「我が家の6歳の子は最初全然クリアできず泣いていましたが、トッテンで挑戦を続けるうちに今では普通のマリオでもクリアできるようになりました」という体験談もあります。マリオUデラックスには何度も失敗したステージでガイド映像を流してくれる救済措置もありますが、親子で相談しながらキャラを変えたり攻略法を工夫したりすることで、ゲームの上達過程自体を楽しめるのが大きなおすすめポイントです。「お母さん抱っこ(マリオが仲間を持ち上げる動作)して~!」と言われたら他のプレイヤーがキノピーチを抱えて大ジャンプしてあげるなど、リアルで助け合う様子がそのままゲーム内にも反映されるのは協力プレイならではの体験でしょう。一度に4人まで遊べますが、大家族で順番待ちが出る場合は交代ルールを決めて1コースごとにメンバーを入れ替えるのも一案です。短いコースが多いのでテンポよく回しやすく、みんなでワイワイ進めます。
年齢別の楽しみ方
- 未就学児: 4歳くらいからトッテンを使えばなんとか操作についていけますが、やはり基本は大人や上の子が一緒にいてあげると安心です。例えば親がマリオで先導し、子は危なくなったらボタン一つでバブル(自分をシャボン玉で包んで飛ぶ)になってもらい、親のところまで運んであげるといった進め方ができます。無理せず「困ったらバブルになっていいよ」と伝えておけば、幼児でもぐずりにくいです。何度やってもうまくいかないコースはスキップして次に進むのも手。「ここはまた今度練習しようね」と声をかけ、できるところから攻略して達成感を積み重ねるのがポイントです。
- 小学校低学年: 5~7歳ならキノピコでプレイすることで随分ミスが減り、自信を持ってクリアできるコースが増えてきます。兄弟で遊ぶ場合、上の子が下の子に「そこジャンプ!」「今だ!」と声をかけてあげる微笑ましい場面もしばしば。協力プレイ中は、逆にお互い邪魔してしまってケンカになることもありますが、それも含めて良い思い出です。もし喧嘩になりそうならチーム分けを変えてみたり、今日は協力してクリアを目指そうと目標を統一するのも手です。低学年くらいになると、子どもだけで秘密の隠しゴールを見つけることもあります。「パパ知らなかった!すごい!」と大げさに驚いてあげれば、子どもは得意顔でますます探索に夢中になるでしょう。
- 小学校高学年: 8~12歳では、家族で遊ぶ場合むしろ子どもの方が先に上達し、大人がついていけないことも出てきます。そんなときは遠慮なく子どもに教えてもらいましょう。「ねえ、そのジャンプのコツ教えて」と聞けば、得意げにアドバイスしてくれるはずです。この年代ではタイムアタックでどれだけ早くクリアできるか挑戦したり、ミス0でクリアする縛りプレイに挑んだりと、遊び方も高度になってきます。マリオUデラックスは昔懐かしい2Dマリオの系譜なので、親世代からすると難しく感じる場面もありますが、子どもたちはゲーム的な思考でどんどん慣れていきます。最後まで親子で協力してピーチ城を奪還した暁には、達成感と家族の一体感を味わえるでしょう。
家族みんなで楽しむ工夫
マリオUデラックスを家族で遊ぶ際のコツは、「上手くいかないことも含めて楽しむ」マインドを共有することです。みんなで遊んでいると、誰かのミスで他の人まで穴に落ちちゃった!なんてハプニングがよく起こります。その度に責めたり落ち込んだりせず、「ドンマイ!次は頑張ろう」「今の面白かったね!」と笑い飛ばす雰囲気を作りましょう。実際プレイ中には、「うちでは子どもがミスして泣きそうになったら、わざとパパも同じ穴に落ちてみせて『ほらパパも落ちちゃった~!痛てて~!』と冗談っぽく言って笑わせます」という工夫をしている家庭もあります。そうすることで、失敗=恥ずかしいことではなくみんなで共有できる出来事になるのです。また、このゲームでは家族の成長を実感できる場面が多々あります。最初はお父さんの後についてくるだけだった子どもが、何回か遊ぶうちに「今度はお父さんとお母さんのミスを指摘してくるくらい」上達することもあります。その変化に気づいたときは、「すごい!もう○○の方が上手だね」としっかり認めてあげましょう。ゲーム内での上達が親にとっても嬉しい驚きとなり、子どもにとっても自信につながります。クリアした後は「次は新作のスーパーマリオワンダーに挑戦してみようか!」といったように、次の目標を親子で共有するのも良いですね。家族でゲームを攻略する過程そのものが、ひとつの冒険物語のように感じられるでしょう。
スーパーマリオメーカー 2
創造力を発揮して遊びたいファミリーには、『スーパーマリオメーカー 2』がおすすめです。対象年齢はCERO:A(全年齢対象)。マリオシリーズのコース(ステージ)を自分で作って遊ぶことができるという、他にはないユニークなゲームです。1人でも十分楽しめますが、家族で協力したり、お互いの作ったコースで対戦したりすることで何倍にも面白さが広がります。
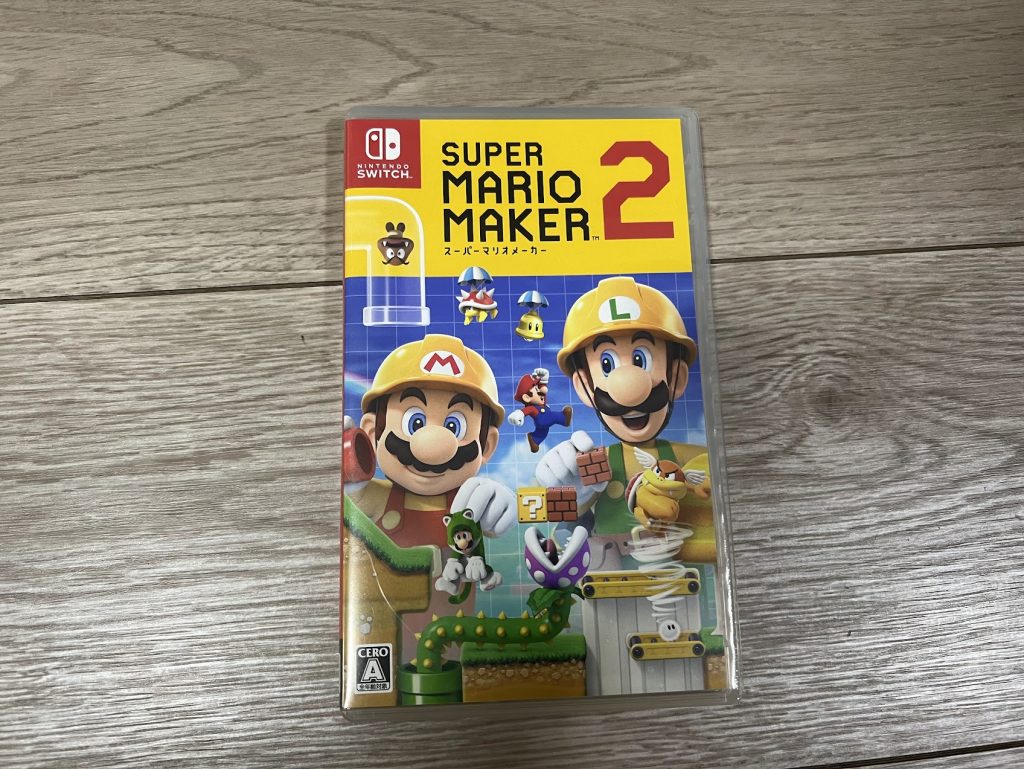
基本情報と遊び方
スーパーマリオメーカー 2では、大きく分けて「コースを作る」と「コースで遊ぶ」の2つの遊び方があります。コースを作るモードでは、Switchの画面上にブロックや土管、敵キャラなどを自由に配置してオリジナルのマリオコースを設計できます。タッチ操作(携帯モード時)やスティック操作で直感的にブロックを並べられるので、難しいプログラミング知識などは一切不要です。兄弟や親子でふたり同時にコースを編集することも可能で、「そこに敵さん置いてみよう!」「もっとコインを増やそうよ」など会話しながらアイデアを形にできます。コースで遊ぶモードでは、自分や他のユーザーが作ったコースに実際に挑戦できます。オフラインでも予めダウンロードした世界中のコースや、Nintendo公式が用意したストーリーモードの100以上のコースで遊べるので、インターネット接続がなくても十分楽しめます。さらに、このゲームは最大4人で同じコースを一緒に遊ぶこともできます(協力してゴールするか、競争するかを選択可能)。家族で力を合わせて難しいコースを攻略したり、誰が一番にゴールできるか競争したりと、遊び方はアイデア次第で無限大です。
子どもと遊ぶときの難易度・おすすめポイント
スーパーマリオメーカー 2は、他のマリオゲームに比べて自由度が高い分、遊び方もプレイヤーに委ねられます。そのため、小さな子には若干ハードルが高そうに思えますが、実際は子どもの想像力と相性抜群のゲームです。例えば、ある小学校2年生の男の子はマリオメーカーで自作のコース作りに夢中になり、「小学2年生の息子はマリオメーカーで自分のコースを作るのが得意」とお母さんが驚くほど複雑な仕掛けを作れるようになったケースもあります。子どもはレゴブロックで遊ぶような感覚でブロックを置き、敵を配置し、オリジナルの冒険を生み出していきます。最初はめちゃくちゃな配置でも大人が「ここにゴールを置いてみようか」と少し助言すれば立派なコースの完成です。おすすめポイントは、家族がお互いに「作ったコースを遊び合う」ことです。子どもが作ったコースに親が挑戦すると、子どもはゲームマスター気分で大はしゃぎします。「ここでびっくりさせようと思ったのに!」「ママそこはジャンプ!」など、自分が考案した罠や仕掛けに親が引っかかると大喜び。逆に親が作ったコースに子どもがチャレンジする場合は、難しすぎないように子どもの好きなパワーアップアイテムを多めに置いてあげたり、途中にメッセージコイン(コインで文字を描ける機能)で「がんばれ!」と応援メッセージを配置したりと、愛情のこもった演出もできます。こうした相互作用により、単なるゲームプレイに留まらず家族間のコミュニケーションツールとして機能するのがマリオメーカーの魅力です。
年齢別の楽しみ方
- 未就学児: 自分でコースを作るのは難しいかもしれませんが、お絵かき感覚でブロックを置くだけでも幼児は楽しめます。3~4歳でも親の膝の上で一緒にやれば、「ここに敵さん置いてみる?」など会話しながら参加できます。子どもの発想は大人が思いつかないようなユニークな配置をすることもあるので、「そんなの置いちゃうの!?」と一緒に笑い合いましょう。遊ぶ方は、ストーリーモードの初級コースなど簡単なものを親子で協力してクリアしてみてください。文字が読めなくてもゴールまでの道筋を探すワクワク感は伝わります。
- 小学校低学年: 6~8歳になると、徐々にコース作りのコツが分かってきます。自分で作ったコースを何度もテストプレイして、「ここ難しすぎるかな?」「もっとコインあった方が嬉しいよね」など改善していく様子は、小さなゲームクリエイターのようです。親は口出ししすぎず、「すごいね!じゃあママに遊ばせて!」と出来上がった作品を尊重して遊んであげましょう。うまくクリアできなくても、「悔しい~もう一回!」と親がムキになって挑戦する姿を見せると、子どもは誇らしげにニヤニヤします。また、家族みんなで1つのコースを順番に遊んでタイムを競うのも盛り上がります。低学年くらいですと、難易度は易しめに作ったほうが達成感を得やすいので、親が一緒にコース作成に参加してバランス調整をしてあげても良いでしょう。
- 小学校高学年: 9~12歳ともなると、かなり凝ったコースを一人で作り上げる子も出てきます。回路のように音符ブロックと敵を組み合わせて自動で音楽が鳴るコースや、パズルのように考えないとクリアできないコースなど、親が感心するアイデアが生まれることもあります。そのような時は全力で称賛し、家族以外の友達にも遊んでもらう機会を作ってあげると良い刺激になります(オンライン投稿機能もありますが、安全面を考えるなら親が管理のもとで)。高学年なら家族4人で難関コースに協力プレイで挑戦することもできます。「一人では無理でも4人ならクリアできた!」という達成感は、チームワークの喜びにつながります。中には家族対抗でコースを作り合って遊ぶ「即興コース対決」なんて楽しみ方をしている家庭もあり、頭を使う遊びとして教育的価値も高いです。
家族みんなで楽しむ工夫
マリオメーカー2を家族で楽しむ鍵は、「発表の場」を作ることです。せっかく作ったコースも誰にも遊んでもらえないと寂しいので、家族内で「○○くんのコース発表会」を開きましょう。作った本人が皆に見どころを解説しながら、他の家族がプレイする様子を見守る時間は格別です。難しいところは「ここ実はヒントがあるんだよ」とニヤリとしながら教えてくれたり、逆に簡単すぎたところはプレイヤー側から「ここもうちょっと敵がいてもいいかもね」なんてフィードバックが出たりと、まるで家族ゲーム開発会議のような盛り上がりになります。また、お題を決めて家族それぞれがコース作りに挑戦するのもおすすめです。例えば「5分以内で作る1画面コース対決」や「今日はお父さんの誕生日プレゼントコースを作ろう」などテーマを設けると、ゲーム内にイベント感が生まれて一層楽しめます。完成したコースはSwitchをテレビに繋いで大画面で発表し、家族全員で拍手喝采しましょう。マリオメーカー2は遊び手でもあり創り手にもなれるゲームです。家族でクリエイティブな時間を共有できるのは、大きな魅力と言えるでしょう。
ルイージマンション3
お化け屋敷探検ゲーム『ルイージマンション3』も、家族で協力して楽しめる名作です。マリオの双子の弟ルイージが主人公で、コミカルなおばけ退治を繰り広げるアクションアドベンチャーとなっています。対象年齢はCERO:A(全年齢対象)ですが、暗いホテルが舞台なので小さな子は怖がる可能性もあります。ただし見た目はポップで可愛らしく、恐怖というよりはドタバタコメディに近い雰囲気なのでご安心ください。オフラインではストーリーモードを2人協力プレイできるほか、最大8人まで遊べるパーティゲームモードも搭載されています。

基本情報と遊び方
ルイージマンション3では、ルイージたち一行が宿泊したホテルが実はおばけ屋敷で、仲間のマリオたちが絵に封印されてしまいます。ルイージは頼りないながらもオバキュームという掃除機型の道具を手に、ホテルの各階を冒険しておばけたちを吸い込み、仲間を助け出すというストーリーです。プレイヤーはルイージを操作し、懐中電灯でおばけを驚かせたり、オバキュームで吸い込んだり、時には叩きつけたりして退治します。特徴的なのは、途中から登場するグーイージというルイージの分身(緑のジェル状キャラ)を切り替えて操作できること。このグーイージ、2人目のプレイヤーが操作可能で、協力プレイ時には一人がルイージ、一人がグーイージとなって一緒に謎解きやバトルを進められるのです。グーイージは体がスライム状なので鉄格子をすり抜けたり、鋭いトゲの罠の上も進めたりする特殊能力があり、2人で協力しないと解けない場面も用意されています。ステージ構成はホテルの階ごとにテーマがあり、映画館フロアや植物だらけのフロアなどバラエティ豊か。単調にならず最後までワクワク探索できます。さらに「プレイランド(ScreamPark)」というおまけモードでは、複数チームに分かれてオバケ退治スコアを競うゲームなどパーティ向けミニゲームが楽しめ、家族大人数で遊ぶのにも向いています。
子どもと遊ぶときの難易度・おすすめポイント
ルイージマンション3は見た目の可愛さとは裏腹に、謎解き要素がしっかりしたゲームです。そのため、小学校低学年くらいまでは大人のサポートがあったほうがスムーズかもしれません。しかし、おばけを吸い込む操作自体は爽快で簡単なので、子どもでも十分楽しめます。協力プレイで親子がルイージとグーイージを担当すれば、「こっち持ち上げて!」「今ライト当てて!」と声を掛け合いながら進むことになり、自然とコミュニケーションが生まれます。6歳のお子さんとお父さんが一緒にプレイした例では、難しい謎解きのヒントは一緒に探し、ボスおばけ戦ではお父さんが相手の気を引きつけている隙に息子さんが背後から攻撃!といった連携でクリアできたそうです。「親子で一緒に謎解きの答えを見つけたとき、ハイタッチして喜びました」という話もあり、協力ならではの達成感があります。また、ルイージが怯えながらも頑張る姿は、臆病な子にも勇気を与えるようです。あるお母さんは「おばけが苦手な息子が、ルイージと一緒なら勇気が出るようで、『ルイージ頑張れ!』と応援しながらプレイしている姿を見ると成長を感じます」といった声もあります。おばけにびっくりするシーンでは、ルイージのリアクションに合わせて子どもと一緒に「きゃー!」と冗談交じりに叫んでみたり、お化けを倒したら「やったね!」と大喜びしたり、恐怖心より達成感を上回らせる演出も効果的です。パーティーモードのプレイランドでは、吸い込んだオバケの数を競うミニゲームなど手軽な遊びもできます。こちらはルールが単純で時間制限内にどれだけ捕まえられるかを争うだけなので、4歳児でもボタンを押しているだけで何匹か取れることもあり、勝敗度外視でワイワイ遊ぶのにピッタリです。
年齢別の楽しみ方
- 未就学児: ストーリーを理解するのは難しいですが、親がメイン操作して子どもが隣で懐中電灯のおばけを指差して「いたよ!」と教えてあげたり、グーイージ役でゆるく参加したりすることは可能です。グーイージはやられてもすぐ復活できるので、小さい子の練習用キャラに向いています。ホテルの雰囲気が怖く感じる場合は、明るい時間帯に遊んだり周囲にお気に入りのぬいぐるみを置いたりして安心感を演出するのも良いでしょう。子どもがおばけを1匹でも吸い込めたら、「すごい!退治できたね!」とたくさん褒め、恐怖心より達成感を上回らせてあげることが大切です。
- 小学校低学年: 7歳前後になれば協力プレイでメインを任せても大丈夫になってきます。親子で頭を突き合わせて謎解きする時間は、まるで一緒にクイズを解いているような盛り上がりです。低学年の子は予想外の発想で「もしかしてこれ吸い込めるんじゃない?」と大人が気付かない仕掛けに気付くこともあるので、「なるほど!やってみよう」とぜひ採用してあげてください。ボス戦では少し難しい操作(タイミングよくボタンを押すなど)が入るため、苦戦したら交代してあげてもOKですが、クリアの瞬間は一緒に味わうようにしましょう。戦い終わったルイージに「ルイージ頑張ったね!」と話しかけてあげると、子どもも自分のことのように誇らしく感じるようです。
- 小学校高学年: 10歳前後になると、ゲームシステムも完全に理解して自力クリアできる子も多いです。ただ、家族で遊ぶならぜひ協力プレイで。高学年にもなると親に手伝ってもらうより、自分が親をリードしてあげる立場になりたがるかもしれません。「次は○○がパパを助けてくれるかな?」とお願いしてみると張り切ってくれるでしょう。プレイランド(パーティーモード)ではチーム戦もできるので、子どもチーム vs 大人チームでミニゲーム対決するのも燃えます。おばけ役と捕まえる役に分かれる非対称ルールなどもあり、戦略性のある対戦に高学年は夢中になります。勝敗にこだわりすぎて悔し泣き…なんてこともあるかもしれませんが、その際は「次は負けないぞ!」と気持ちを切り替えさせて、リベンジマッチに臨みましょう。
家族みんなで楽しむ工夫
ルイージマンション3を家族で楽しむポイントは、協力ミッション感を演出することです。物語上もルイージが勇者としてみんなを救う展開なので、家族内でも「ルイージ救出隊」を結成しましょう。例えば「お母さんは地図係ね」「○○ちゃん(子ども)はアイテム係で、宝石(隠し収集アイテム)見つけたら教えて!」という風に、実際の役割を与えると、一緒に冒険している気分が高まります。ゲーム内の手帳に書かれるヒントも家族で声に出して読み合うと、「なるほど、こうしろって!」と頭に入りやすく子どもも理解を共有できます。おばけにびっくりするシーンでは、わざと大げさに家族で「きゃー!」とリアクションして笑いに変えてしまうのも雰囲気を和ませます。さらに、イベント的な工夫としてはホテルを攻略するごとに”称号”を作ってあげるのも面白いです。例えば5階までクリアしたら子どもに「ゴーストハンター5級認定!」と紙に書いた手作り認定証を渡すなどすれば、子どもは大喜びで続きを頑張るでしょう。祖父母も交えて8人までできるミニゲームでは、単純操作で楽しめるのでゲームに不慣れな方にも声をかけてみてください。みんなでコントローラーを持ち、画面の中のおばけを追いかけ回す姿は、見ている人も含めて爆笑必至です。
子どもの年齢別で見るマリオゲームの楽しみ方
ここまで各ゲームごとに年齢に触れてきましたが、改めて年齢別にマリオゲームを楽しむポイントをまとめてみましょう。子どもの成長段階に応じて、ゲームとの関わり方も変化します。無理なく楽しめる遊び方を知っておけば、親としても適切にサポートできます。
未就学児(3~6歳くらい)
この年代の子どもは、とにかく興味と好奇心の塊です。マリオキャラクターのカラフルな世界やコミカルな動きは、それだけで幼児を引き付けます。ただし、自分でコントローラーを思い通りに操作するのはまだ難しい時期でもあります。未就学児と一緒に遊ぶ際のポイントは以下の通りです。
- 観るだけでも楽しい: 子どもによっては、親がプレイするのを横で見ているだけで満足するケースも。無理にプレイさせようとせず、「一緒に見ようね」と実況交えて見せてあげるのも立派な参加です。ゲーム画面を大きめのテレビに映せば、子どもも絵本やアニメを見るような感覚で楽しめます。
- 簡単な役割を任せる: コントローラーを握りたがる子には、Joy-Con片方だけ渡して簡単な操作をお願いしましょう。例えばマリオカートでアクセルだけ押してもらう、マリオパーティの単純なミニゲームを担当してもらうなど、できる範囲で「自分もやってる」感覚を持たせてあげます。
- 協力プレイでサポート: 複数人プレイ対応のゲームでは、大人がしっかり周りをケアしつつ子どもにも好きに動いてもらいましょう。子どもがミスしても大丈夫な仕組み(例:泡になれる、すぐ復活できる等)を活用し、「○○ちゃんのおかげで助かったよ!」と些細なことでも持ち上げてあげると喜びます。
- 短い時間で区切る: 幼児は集中力が短いので、ゲームは15~30分程度で一度切り上げ、休憩や他の遊びを挟むと良いです。マリオのゲームは区切りがつけやすい(1レース、1コース、1ミニゲームなど)ので、「あと○○したらおしまいね」と予告して遊ぶ習慣をつけましょう。
- 成功体験を大事に: 小さなことでもクリアできたら大げさに褒め、失敗して泣きそうになったらすかさず別の楽しい要素に目を向けさせます。勝ち負けより「楽しかったね!」の気持ちで終われるよう、親が誘導してあげることが肝心です。
小学生低学年(6~9歳くらい)
小学校に入るとルールや勝敗の概念も理解し、操作技術も飛躍的に向上します。しかしまだまだ集中力や我慢強さは発展途中。低学年とゲームをする際のポイントは以下です。
- ルールを理解させる: マリオパーティのスゴロクの流れや、テニスの得点の数え方など、ゲームの基本ルールは丁寧に説明しましょう。理解できると自分なりの目標を持って取り組めるようになります。逆に意味が分からないままだと興味を失いやすいので、「コインを20枚集めるとスターと交換できるんだよ」等わかりやすい言葉で教えます。
- 達成感を味わわせる: 簡単すぎると退屈、難しすぎると嫌になるのがこの年頃。程よい難易度で達成感を得られる工夫が必要です。例えばマリオUデラックスならキノピコで挑戦してクリア→次は通常マリオでクリア、というようにステップアップさせるなど、チャレンジ目標を段階的に設定するのも効果的です。
- 負ける悔しさと向き合う: この時期は負けず嫌いが強く出て、ゲームで負けて大泣き…なんてことも。しかし、ゲームは勝ち負けがあるもの。悔しさをバネに「次はこうしよう」と考えたり、負けても相手を称える姿勢を学ぶ良い機会です。親が率先して「負けちゃったけど楽しかった!またやろうね」と言ってあげたり、兄弟げんかになりそうならルールを整えてあげたりしながら、健全な競争心とスポーツマンシップを育てましょう。
- 一緒に考える時間を: パズルや謎解き系の場面では、子ども一人に任せず一緒に頭をひねると良いです。「ここどうすればいいかな?」「○○はどう思う?」と問いかけ、子どもの発想を引き出してみましょう。自分の考えを採用して問題が解決すると、子どもは大きな誇りを感じます。
- ゲーム以外への発展: 低学年くらいだと、ゲームの世界観を日常に取り入れたごっこ遊びや創作遊びも大好きです。絵を描いたり、粘土でマリオキャラを作ったり、マリオカートごっこと称しておもちゃの車で競争したり、ゲームから得たアイデアで現実遊びをクリエイティブに広げられるよう促すのも素敵なアプローチです。
小学生高学年(10~12歳くらい)
高学年になると身体能力・知力とも発達し、大人顔負けのプレイを見せる子もいます。反面、思春期に差し掛かり親と遊ぶのを恥ずかしがる場合もあるでしょう。この年代と向き合うポイントは以下です。
- 対等なプレイヤーとして扱う: ここまで来れば子どもも一人のゲーマーです。親だからといって手加減しすぎたり子ども扱いしないこと。むしろ公平に勝負し、お互い本気で競い合うことで、子どもは「大人に勝った!」「本気のパパ強い!」と真剣勝負を楽しめます。もちろん勝った負けたで嫌な雰囲気はNGなので、終わった後はしっかり労い合うこと。
- ゲームマナーやモラルを教える: オンライン対戦に興味を持つ子も増える時期ですが、家庭内でまずオフラインプレイを通じてマナー教育をしましょう。例えば「腹が立ってもコントローラーを投げない」「暴言を吐かない」「順番を守る」等。当たり前ですが、ゲームに熱中すると忘れがちな点です。家族内ルールを決め、守れなかったら一旦中断するといった形で、健全な遊び方を身につけさせます。
- 子どもの得意を尊重する: 高学年ともなると、親よりゲームが上手になるケースも多いです。そこで無理に親が勝とうとしたりミスを指摘しすぎるのは逆効果。子どもの得意なプレイ(例えばマリオメーカーで斬新なコースを作れる等)を心から称賛し、教えてもらう姿勢も見せましょう。親が自分に一目置いてくれると感じることで、自己肯定感がアップします。
- ゲームの裏側にも興味を: 単に遊ぶだけでなく、「どうしてこんな仕掛け思いついたんだろうね?」などゲーム制作の視点や戦略の理論などに話を広げてみると、子どもの好奇心を刺激します。マリオの歴史やキャラクター設定など豆知識を一緒に調べてみるのも楽しいでしょう。そうしたメタな話題も共有できると、親子の会話がより深まります。
- 自分たちのスタイルを確立: 高学年にもなると各家庭でゲームとの付き合い方が固まってくる頃です。毎週末は家族でゲーム大会、誕生日には新しいゲームをみんなで遊ぶ、成績が良かったらご褒美にゲーム時間延長等、それぞれの家庭ルールや行事と絡めたスタイルができると、ゲームがポジティブな生活の一部として根付きます。子ども自身にも「うちでは家族でゲームするのが当たり前で楽しいこと」と認識され、健全な遊びとして継続しやすくなります。
オフラインプレイならではの魅力
昨今はオンラインゲームも隆盛ですが、家族で楽しむなら断然オフラインプレイ(画面を共有した同じ空間でのプレイ)に軍配が上がります。Nintendo Switchは据置機と携帯機のハイブリッドで、リビングのテレビでもテーブル上でも手軽に複数人プレイができるため、家族団らんにピッタリです。オフラインプレイ中心で遊ぶことの魅力を整理してみましょう。
- コミュニケーションが生まれる: 同じ部屋で顔を合わせながら遊ぶことで、自然と会話や笑い声が増えます。「今の見た!?」「次はこっち行こうよ」「頑張れー!」など、オンライン越しでは味わえない生のリアクションがあります。ゲーム中の子どもの表情や仕草を見て取れるので、親も安心感がありますし、子どももすぐ親に自慢したり甘えたりできます。
- 助け合える: オフラインで隣にいれば、わからない操作をその場で教えたり、コントローラーを交代してフォローしたりがスムーズです。特に小さな子は、「ここ押してごらん」と親が指を添えてあげるだけでクリアできたりします。また、兄弟同士で「じゃあ次は僕がやってあげるね」と自主的に助け合う場面も出てきます。家族の絆が深まる瞬間です。
- 安全で安心: オフラインならインターネット経由の見知らぬ相手と接触することがありません。小さい子がいる場合、ネット上のトラブルや有害なやり取りの心配をしなくて済むのは大きな利点です。また、Nintendo Switchでは画面分割や一画面共有型のゲームが多く、全員が一つのスクリーンを見て遊ぶため、親がプレイ内容を把握しやすいです。子どもが何をしているか見守れるので安心感があります。
- みんなで画面を囲める: テレビモードなら大画面で迫力満点、テーブルモードなら例えばキッチンテーブルや旅行先の新幹線でも向かい合わせで遊べます。「おすそわけプレイ」でJoy-Conさえ人数分あれば場所を選ばず盛り上がれるのはSwitchの強みです。リビングでソファに座って家族で肩を並べながらコントローラーを操作すれば、それだけで一体感が生まれます。
- その場でアナログ要素をプラス: オフラインだからこそ、リアルな遊びとの融合も容易です。例えばスコアをホワイトボードに書いて貼り出す、ゲーム内大会のトーナメント表を紙で作る、応援用の旗を子どもと作って振る、勝者に家族からトロフィー(手作りでもOK)を授与する…など、ちょっとした工作や仕掛けをその場で用意してゲーム体験を彩れます。家全体がゲームセンターや舞台のような盛り上がりになることも。
- 時間管理がしやすい: みんなで遊ぶ場合、親が主導して「じゃあ今日はここまで」と切り上げやすいです。オンラインだとキリがつかなかったり相手がいるからやめにくかったりしますが、家族内でオフラインなら「次で終わりね」とルール化しやすく、ゲーム時間をコントロールできます。遊び終わった後も全員が揃っているので、「楽しかったね」とすぐ感想戦をしたり、そこから別の家族活動にスムーズに移行できたりします。
- ノスタルジーと記憶に残る: オフラインマルチプレイの体験は将来にわたって家族の思い出となります。大人になった子どもが「あのとき家族でマリオカートやったよね」と懐かしむような、かけがえのない記憶を共有できるのは、目の前で一緒に遊んだからこそです。親にとっても、子どもが初めて自分に勝った日のことや、みんなで大笑いしたハプニングなど、写真や動画には残らなくても心に刻まれるシーンがたくさん生まれるでしょう。
総じて、オフラインプレイは家族団らんそのものです。マリオゲームは一人用のものでも画面を通して皆でワイワイできますし、マルチプレイ対応作ならなおさら絆を深める道具になります。ぜひ積極的にリビングにSwitchを持ち出して、家族のコミュニケーションツールとしてのゲームを楽しんでください。
ゲームを通じて育まれる子どもの力
ゲームは単なる遊びと思われがちですが、家族で向き合ってプレイすることで、子どもの心や能力の成長につながる側面も多々あります。マリオシリーズのゲームを一緒に遊ぶ中で、どんな感情や学びが得られるのか、いくつかの観点から見てみましょう。
- 勝ち負けの経験: マリオカートやマリオパーティなど勝敗がはっきりするゲームでは、子どもは「勝つ嬉しさ」と「負ける悔しさ」の両方を体験します。勝てば自信につながり、負ければ悔しくて涙…なんてこともあるでしょう。しかし、ここで家族が適切にフォローすることで、負けたときの気持ちの整理や、再挑戦する気概を学べます。何度負けても挑み続け、ついに勝利したときの達成感は大きな自信となりますし、他人が勝った時に拍手を送る大切さも知っていきます。ゲームという安全な環境で、競争と協調の精神を養えるのは大きなメリットです。
- コミュニケーション力: 協力プレイでは特に、仲間とのコミュニケーションが重要になります。ルイージマンションでの「せーの!」やスーパーマリオの「待って、一緒にジャンプしよう」など、声を掛け合い相談しながら進めるうちに、子どもは自分の考えを伝える力や、人の話を聞く姿勢を身につけます。兄弟間でも「次は僕がやる?」「ありがとう、助かったよ」といった言葉が自然と出てきて、日常生活にも良い影響が現れることがあります。親子間でも、ゲーム中の会話を通して普段あまり見せない子どもの一面(頼もしいところ、優しいところ、負けん気の強さetc.)を知り、理解が深まるでしょう。
- 思考力・問題解決力: ペーパーマリオの謎解きや、マリオメーカーでのコース設計、マリオパーティのミニゲームなど、マリオシリーズには考えて攻略する要素が数多くあります。子どもは楽しみながら論理的思考や創造力を発揮し、「どうすればうまくいくか」を試行錯誤します。例えばパズルを解くとき、一度失敗しても「次は違う方法を試してみよう」と発想を転換する柔軟性が育ちますし、マリオメーカーで自分のアイデアを形にする過程では創意工夫する力が磨かれます。親御さんから見ても、ゲームを通じて子どもの頭がフル回転している様子は頼もしいものです。
- 空間認識・反射神経: アクションゲーム全般に言えますが、マリオのゲームはキャラや車を思い通りに動かすために、タイミングよくボタンを押したり距離感を測ったりする必要があります。遊んでいくうちに自然と空間把握能力や反射神経が鍛えられます。特にマリオカートでコーナーを曲がる感覚、マリオのジャンプの着地点を見極める勘などは、手と目の協調動作(ハンド・アイ・コーディネーション)を促進し、スポーツにも通じる基礎能力を養います。子どもは吸収が早いので、大人が舌を巻くほどのプレイスキルを身につけることもしばしば。このような身体的な感覚も遊びながら鍛えられるのは嬉しい副産物です。
- 忍耐力と達成感: 難しいステージや手強いボスに挑むとき、子どもは壁にぶつかります。何度失敗しても諦めずチャレンジを続ける体験は、忍耐力や継続力を育てます。家族が励ましつつ見守り、クリアできたときは皆で大いに褒め称えることで、「頑張ればできるんだ!」という自己効力感を得られます。現実の勉強やスポーツでも、同様の粘り強さを発揮するきっかけになるかもしれません。マリオシリーズは絶妙に「あと少しでできそう!」と思わせるバランスで設計されているので、子どももトライ&エラーを繰り返しやすく、達成した喜びが自信に繋がりやすいです。
- 創造性・表現力: マリオメーカーでコースを作ったり、家族でゲームのまねっこ遊びをしたりする中で、子どものクリエイティビティが刺激されます。「こんなステージあったら面白いかも」「マリオみたいなお話を考えてみようかな」など、ゲームからインスピレーションを得て自主的な遊びへと発展するケースも多々あります。ゲーム中に描かれる世界観やキャラクターの個性に触れることで、子どもは自分なりの想像を広げ、それを絵や言葉、動きで表現しようとします。親はぜひそれを受け止め、共感してあげてください。たとえ荒唐無稽な発想でも、「いいね!面白そう」と肯定することで、子どもの表現意欲は大きく伸びていきます。
- 家族愛・安心感: 何より、家族で楽しく遊んだ記憶は子どもにとってかけがえのない安心感となります。嫌なことがあっても「あのとき家族で大笑いしたな」「お父さんお母さんが自分のために時間を作ってくれる」と思い出せることで、心の支えになるでしょう。ゲームを通して感じた家族の愛情や一体感は、子どもの自己肯定感や精神的安定にも寄与します。「うちの家族はチームだ」「僕の家族は最高に楽しい」と思えることは、子どもの幸福感につながり、健やかな成長を後押しします。
もちろんゲームのやりすぎには注意が必要ですが、適切に付き合えばマリオゲームは子どもの成長の良きパートナーになり得ます。親子でプレイしながら、ぜひお子さんの心の動きや成長の芽生えを感じ取ってみてください。
家庭内イベントで盛り上がる遊び方アイデア
ゲームは日常の合間の娯楽でもありますが、せっかく家族で遊ぶならちょっとしたイベントとして演出してみるのもおすすめです。誕生日や週末、雨の日など、家族が一緒にいる機会にマリオゲームを取り入れて、思い出深いひとときを演出するアイデアをいくつかご紹介します。
- 誕生日パーティーにマリオ大会: お子さんの誕生日や家族のお祝い日に、マリオゲーム大会を企画してみましょう。例えば「○○ちゃん○歳記念 マリオカート杯」と称して、家族でグランプリ4レースを開催します。手作りの優勝メダルやトロフィー(紙や段ボールでOK)を用意し、1位の人には主役の子から授与してもらう、なんてセレモニーを組み込むと特別感が増します。マリオパーティであれば、ボードゲーム1回を誕生日モードにして、マップ上にプレゼントの絵を貼ったり、ミニゲームで勝った人から順にケーキを食べられる権利が与えられる(負けた人はローソクの火を消す役!)などユニークなルールを足しても楽しいでしょう。主役のお子さんが大好きなキャラクター(マリオやピーチ)のコスプレ風帽子やグッズを身につけてプレイするのも写真映えします。
- 週末の定期ゲームナイト: 毎週または隔週の週末に「ファミリーゲームナイト」を設定してみるのはいかがでしょう。土曜の夜は家族みんなでテレビの前に集まり、1時間だけマリオゲームをする時間、というように決めます。例えば第1土曜はマリオパーティでミニゲーム大会、第2土曜はマリオテニスでリーグ戦、第3土曜は子どもが作ったマリオメーカーコース発表会…とテーマを変えても良いですし、その時の気分でみんながやりたいゲームを選ぶフリーでもOKです。定期イベント化することで、子どもは「ゲームナイトが待ち遠しい!」と日々の励みになりますし、家族の習慣として根付けば一体感も高まります。最後に簡単な振り返り(「今日のMVPはお母さん!」「次は負けないぞ~」)など冗談交じりに語り合って締めると、ほっこりした気持ちで週末を終えられます。
- 雨の日の室内運動会: 外遊びできない雨の日こそ、Switchの出番です。運動エネルギーを持て余している子には、マリオテニス エースのスイングモードで室内テニス大会を提案しましょう。家具や周囲に注意しつつ、リビングがミニテニスコートに早変わりです。交互にペアを組んで総当たり戦をしたり、家族vsCOM(CPU)で勝てるか挑んだり、体を動かすプレイでリフレッシュできます。マリオパーティにも体を使うミニゲームがあるので、雨音に負けないくらいの笑い声と歓声で家の中を明るくできますよ。終わった後はみんなで水分補給し、「いい運動になったね」と爽快感を共有しましょう。
- 長期休みの家族マリオ検定: 夏休みや冬休みなどには、じっくり時間を取って家族で「マリオ検定」に挑戦するのもユニークです。例えば夏休み期間中に複数のマリオゲーム(カート、パーティ、メーカーなど)を総合的に遊び、その成果をもとに「マリオマスター認定証」を作ります。項目として、「コイン1000枚以上集めた」「自作コース5つ作った」「50ccから150ccまでクリア」など子どもと一緒に目標を立て、達成具合をチェックシートに○付けしていくと良いでしょう。全部クリアしたら晴れて家族全員「マリオマスター」として認定!手書きの認定証や賞状を渡してあげれば、達成感もひとしおです。自由研究代わりに、ゲーム内で分かったこと(キャラの名前、技、面白かった場面)をまとめてみるのも良いですね。
- お正月&年末ゲーム初め・納め: お正月は福笑いならぬ「マリ笑い」で、新年最初の笑いをゲームで取るのはいかがでしょう。元旦に家族でマリオパーティをして初笑い、なんて健康的です。逆に年末は「今年の遊び納め」として、大晦日に1年を振り返りながら家族マリオ大会を開きましょう。例えば「〇〇家ゲームAWARDS」と銘打ち、「今年一番の名場面賞」「ベストプレイヤー賞」などを勝手に決めて発表します。「5歳の妹が初めて1位になったレースが感動賞!」など家族だけの表彰で大盛り上がり間違いなし。それくらい大げさにエンタメ化しても、家族ならノリノリで楽しめますね。
このように、マリオゲームは少しの工夫で家庭イベントの主役になります。大事なのは、家族みんなで全力で楽しむことを恥ずかしがらないこと。お父さんお母さんが本気で盛り上げれば、子どもたちも存分に乗ってきます。「ゲームばかりして…」と否定的になるより、「せっかくならレクリエーションにしちゃおう!」という発想で、日常に彩りを加えてみましょう。
保護者がゲームを選ぶときのポイント
いざNintendo Switchでマリオゲームを遊ぼうとなったとき、保護者としてはどのタイトルを選ぶか、そして遊ぶ際に何に気をつけるべきか気になることでしょう。ここでは、親目線でチェックしておきたいポイントをまとめました。
- 対象年齢・難易度: 基本的にマリオシリーズはCERO:A(全年齢対象)ですが、難易度や内容の適性はゲームによって異なります。例えば、アクション初心者の幼児にはマリオカートやマリオパーティがとっつきやすいですし、多少ゲーム慣れした小学生ならマリオUデラックスやマリオワンダーも十分楽しめます。ストーリーを読み解く力が必要なペーパーマリオは、読み聞かせできる環境か小学校中学年以上が目安でしょう。お子さんの年齢・経験に合わせて「無理なく遊べそうか」「サポートすれば遊べるか」を判断材料にしましょう。迷ったら店頭や公式サイトの対象年齢マーク(CERO区分)や紹介文を参考にするのも手です。
- プレイ人数: 家族の人数とゲームの対応人数も重要です。4人家族なら、4人同時プレイ対応のゲーム(マリオカート8DX、マリオパーティ、マリオUデラックス、マリオワンダー、マリオメーカー2の一部モードなど)が皆でできて理想です。一方、ペーパーマリオのように1人用だったりルイージマンション3のストーリーのように2人までのものもあるので、その場合は交代プレイや見守り参加でうまく全員が関われる形を考えましょう。家族5人以上で遊ぶ場合は、プレイランド(ルイージマンションの8人対戦)やマリオパーティで交代制にするなど工夫が要ります。
- セーブや中断のしやすさ: 子どもは突発的な用事や気分の変化でゲームを中断することもあります。「セーブしないとやめられない」と長引かないように、セーブ方法は事前に把握しておきたいポイントです。マリオパーティは基本中断セーブができない(短いゲームなので割り切り)ので開始タイミングに注意、ペーパーマリオは決められたポイントでセーブ、マリオUデラックスはいつでも中断セーブ可能だが再開するとセーブが消える等、それぞれ仕様があります。親御さんは説明書や公式サイトでセーブの仕組みをチェックし、適度なところで区切れるよう誘導してあげると良いでしょう。
- 難易度設定・アシスト機能: 最近のマリオゲームには初心者サポートの機能が充実しています。例えばマリオカート8DXのハンドルアシスト/オートアクセルはオンにするだけで幼児でもレースを完走できますし、マリオUデラックスには前述の無敵キャラやガイド映像、マリオワンダーにはダメージ無効キャラやバッジ機能があります。購入前にこれらの存在を知っておくと、いざ遊ぶときに「この子にはこの設定を使おう」と柔軟にカスタマイズできます。また、反対にゲームに慣れてきたらアシストをオフにしてみるなど、難易度を調整して飽きさせない工夫もできます。親が各ゲームの設定項目を先に確認し、子どもの上達度合いに応じて提案してあげましょう。
- 暴力性・安全性: マリオシリーズは基本的にコミカルで残酷な表現はありません。おばけを捕まえるルイージマンションも怖すぎる演出は避けられています。ただ、一部で軽いホラー要素(驚かせ)があったり、ペーパーマリオでちょっぴり切ないストーリー展開があったりします。しかしいずれも全年齢対象の範疇なので、内容面で過度に心配する必要はないでしょう。それよりも安全面では、Joy-Conを振るゲームでは必ずストラップを付けさせる、狭い場所で走り回らない、画面の見すぎによる目の休憩を取らせる等、物理的・健康的な注意を促すことが親の役目です。また、オフライン中心なのでネットの危険性は低いものの、マリオメーカー2でオンライン投稿を見る際などは保護者が内容をチェックするなど見守りを忘れずに。
- ゲーム機の設定: Switch本体にはペアレンタルコントロール機能があり、1日のプレイ時間や使用できるソフトを制限できます。もし長時間プレイが心配なら、最初から時間制限を設けておくと安心です。具体的には、1日○時間でタイマー通知、夜9時以降はゲーム不可等の設定がスマホアプリから簡単に行えます。子どもが約束を守れるうちはゆるく、難しい時期は厳しくと、家庭ルールに応じて活用してみましょう。また、コントローラーは人数分用意しておく(最低Joy-Con2セットで4人プレイ可能)ことや、テレビモードで遊ぶなら画面の高さ調整など、環境面も事前に整備しておくとスムーズです。
- 価格とコスパ: ゲームソフトは決して安い買い物ではないので、予算や遊びたい期間も考慮しましょう。マリオシリーズは大抵定価5000~6000円台ですが、それに見合うボリュームとリプレイ性があります。例えばマリオカート8DXやマリオメーカー2は繰り返し何年も遊べ、家族皆で楽しめるのでコスパ抜群です。逆に一度クリアすると終わりがちなペーパーマリオなどは、子どもがクリアしたら他の兄弟や親がストーリーを追体験することで無駄なく楽しめます。DLC(追加コンテンツ)の有無も確認ポイントですが、マリオシリーズではマリオカートの追加コース(有料パス)ぐらいで、なくても十分遊べます。購入時は任天堂公式ストアや量販店の子ども向けソフトコーナーをチェックし、キャンペーンやセット商品などお得な情報も見逃さないようにしましょう。
最後に、保護者自身もゲームを一緒に楽しむ心構えが大切です。子どもは敏感なので、親が嫌々付き合っていると感じると素直に楽しめません。ぜひ前向きに「これ面白そうだね!」「パパも昔マリオ好きだったんだよ」など話しかけ、家族で遊ぶ時間を肯定的に捉えてください。安全面と時間管理の舵取りさえしっかりすれば、あとは子どもと同じ目線でマリオの世界に飛び込んでOKです。そうすることで、親子の信頼関係もより深まり、ゲーム選びからプレイ中、そして終わった後まで、笑顔あふれるひとときになるでしょう。
家族の体験談あれこれ
実際にNintendo Switchのマリオゲームを家族で楽しんでいるご家庭からは、さまざまなエピソードや感想が寄せられています。その一部をご紹介します(内容は創作エピソードですが、リアルな声をイメージしています)。
- マリオカート8 デラックス: 「5歳の娘はアイテムで相手を逆転するのが大好きで、『やった!当たった!』と大喜びします。一番のお気に入りはスターで無敵になってダッシュすること。小さな妹が遊ぶときはハンドルアシストを使うので、壁にぶつからず走れてニコニコしています。最近は娘に全く勝てず、父としては嬉しいような悔しいような…(笑)家族4人でわいわい盛り上がる、我が家の定番ゲームです。」
- スーパー マリオパーティ: 「うちには3歳と7歳の兄妹がいます。マリオパーティではお兄ちゃんがサイコロを振って進め、妹はミニゲームだけ一緒にやっています。4歳の頃はルールがわからず泣いてしまうこともありましたが、今では妹も『次は1が出るといいな~』なんて言いながらサイコロを振ろうとします。ミニゲームで妹が偶然勝ったとき、お兄ちゃんが『○○ちゃんすごい!』とハイタッチしてあげたのには成長を感じました。」
- マリオテニス エース: 「ゲーム好きの父(私)とスポーツ好きの母、そして小学2年の息子と幼稚園の娘という家族構成です。マリオテニス エースは家族みんなのお気に入り。特にスイングモードではリビングがテニスコートに早変わりします。娘(5歳)はルールはよく分かってませんが、Joy-Conを振り回してボールに当てるだけで大笑い。息子(8歳)は最近スタンダードモードで私を打ち負かすほど上達しました。おかげで父は本物のテニスでは敵いませんが、ゲームではまだ負けられません(笑)。おじいちゃんも交えてダブルスをやったときは、世代を超えて超白熱しました!」
- ペーパーマリオ オリガミキング: 「小学1年の娘と一緒に少しずつ物語を進めています。ひらがなは読めますが漢字は難しいので、私がセリフを読み上げながら進めるスタイルです。まるで絵本を一緒に読んでいるようで、娘はオリビア(相棒キャラ)のセリフを真似したり、おどけたシーンで声を上げて笑ったりしています。戦闘のパズルはまだ娘には難しいので、『どうする?お母さんやっていい?』と聞きつつ私が解いています。でもラスボス手前では、『ママもう教えなくていい、私がやる!』と自力で並べ替えに挑戦。時間はかかりましたが、自分で最後までクリアできたときの誇らしげな顔は忘れられません。娘にとってゲームの主人公の活躍と自分の成長が重なったようです。」
- スーパーマリオブラザーズ ワンダー: 「発売日に家族でワクワクしながら始めました!小5の兄、小2の妹、そして親の4人で一斉に同じコースを冒険できるのが新鮮でした。画面内はカオスですが(笑)、兄が妹に『そこ敵いるよ!ジャンプジャンプ!』と教えたり、私がやられそうになると娘がヨッシーで背負って助けてくれたり、チームワーク満点です。ワンダーフラワーで世界が変わる演出には、みんなで「うおお!」と叫びました。難しそうなコースも、兄はバッジで二段ジャンプを付けて攻略、妹は無敵ヨッシーでニコニコついてきて、それぞれの楽しみ方ができています。エンディングを迎えた後、『家族でクリアできたね!』と4人でハイタッチした瞬間は最高でした。」
- New スーパーマリオブラザーズ U デラックス: 「ゲーム初心者だった年中の息子のデビュー作がこれでした。最初はマリオで全然クリアできず『難しいよ~』と泣いてしまったので、すかさず『じゃあトッテン(無敵キャラ)でやってみよう!』と変更。敵に当たっても平気なので、自信を持って走り回れるようになりました。私が先導しつつ、息子は泡でついてきたり、自力でゴールまで行けたりと、日に日に上達。今ではトッテン卒業して立派にマリオやルイージでステージを攻略しています。6歳の誕生日目前にクッパを倒せたときは、『すごい!もうパパより上手だね』と大げさに抱きしめたら、照れ臭そうに笑っていました。クリア後、『次はワンダー買って』と言われて、親も嬉しい悲鳴です(笑)。」
- スーパーマリオメーカー 2: 「小学4年の息子はこのゲームで才能を開花させました。最初は遊ぶ専門でしたが、ある日からコース作りにハマりだし、今では私が驚くような凝った仕掛けのコースを作ります。家族でそれを遊ぶのが最近の我が家のブーム。『ここどうやってクリアするの!?』と私や妻が四苦八苦している横で、息子はニヤニヤ。解けたときは一家で拍手喝采です。下の娘(6歳)も兄の真似をしてコースを作りますが、敵だらけ・スターだらけのめちゃくちゃコース。それはそれでみんなで爆笑しながら遊んでいます。子どもたちが遊びの“創り手”になれる姿を見て、ゲームの良さを実感しています。」
- ルイージマンション3: 「怖がりな7歳の息子でしたが、ルイージマンション3は興味津々で一緒にプレイしました。一人では進めないので、私(母)がルイージ、息子がグーイージ役で協力。薄暗いホテルにビクビクしていた息子も、オバキュームでおばけを吸い込む爽快感がわかったら『ボクに任せて!』と前に出るように。夜のプレイは怖がるので休日の昼間限定で少しずつ進め、最後には「ルイージ頑張ったね~!」と親子で抱き合って感動しちゃいました。エンディング後、息子は少しお兄さんになった気がしたのか、『次はパパと2人でやってあげてもいいよ?』なんて言っています(笑)。家族で謎解きしながら進む過程が、本当に脱出ゲームに挑戦しているみたいで楽しかったです。」
どのエピソードからも、家族でマリオゲームを遊ぶ楽しさが伝わってきますね。それぞれの家庭でドラマがあり、笑いがあり、成長があり…。ぜひ、あなたのご家族でもマリオゲームを通じて素敵な物語を作ってみてください。
どのゲームから始める?初心者ファミリーにおすすめのルート
「Nintendo Switchを買ったけど、まずどのマリオゲームから遊べばいい?」という初心者ファミリーの声も多いでしょう。マリオシリーズはどれも魅力的なので迷ってしまいますが、子どもの年齢や好みに応じて順番を考えるとよりスムーズに楽しめます。ここでは、いくつかおすすめのスタートルートをご提案します。
- まずは手軽に盛り上がれるゲームから: ゲーム初心者のファミリーには、取っ付きやすくルールが単純な『マリオカート8 デラックス』や『スーパー マリオパーティ』がおすすめです。マリオカートなら操作も単純で即盛り上がれ、パーティゲームなら子どもが失敗しても笑いに変えやすいです。この2つは「Switch 家族向けソフト」の鉄板とも言えるので、最初の1本として間違いありません。実際、「初めてのSwitchソフトはマリオカートで、子どもと一緒に遊ぶうちに家族全員ゲーマーになった!」という話もよく聞きます。
- 次に協力プレイや創造性が楽しめるゲーム: 基本的な操作に慣れてきたら、家族で協力できる『New スーパーマリオブラザーズ U デラックス』や、自由度の高い『スーパーマリオメーカー 2』に挑戦してみましょう。マリオUデラックスでは4人同時プレイで助け合う体験ができ、ゲームならではのチームワークが育まれます。マリオメーカー2では、遊ぶだけでなく作る楽しさに目覚めるかもしれません。この段階では子どももゲームにある程度慣れてきているので、新しい遊び方にもスムーズに入れるでしょう。
- 余裕が出てきたら物語性のあるゲーム: 子どもがゲームに慣れ親しみ、読み書きや考える力もついてきたら、『ペーパーマリオ オリガミキング』や『ルイージマンション3』といったストーリー重視のゲームも検討してみてください。これらは一人用がメインですが、親子で交互に操作したり一緒に謎を解いたりすることで、また違った楽しみが味わえます。物語を共有する体験は、親子の会話にも花を咲かせます。「初心者ファミリーだけど、子どもがマリオの世界観にどっぷり浸かるストーリーも体験させたい」という場合、このステップに進んでみましょう。
- 最新作や人気作にもチャレンジ: 基礎固めができたら、ぜひ話題の最新マリオゲームにも手を出してみましょう。『スーパーマリオブラザーズ ワンダー』は最新2Dマリオとして新規性たっぷりで、家族での驚き体験に最適です。また、もしまだプレイしていないなら『スーパーマリオ オデッセイ』(3Dマリオの大冒険、2人でマリオと帽子のCappyを操作可能)なども家族で遊ぶと盛り上がります。マリオシリーズ初心者ファミリーでも、これまでのゲームで十分腕を磨いていれば新たなチャレンジも問題なく楽しめるはずです。
- 子どもの興味に合わせて番外編も: マリオシリーズ以外にもSwitchには家族向けの名作がたくさんあります。例えば子どもが工作好きなら『Nintendo Labo』で段ボール工作&ゲーム体験を、運動好きなら『リングフィット アドベンチャー』で体を動かすRPGを、といったように興味に合ったソフトを織り交ぜるのも一案です。マリオゲームでゲーム自体に親しんだあとは、視野を広げて他のファミリーソフトも検討してみましょう。ただし、最終的にはまたマリオの楽しさが恋しくなって戻ってくるかも? そんなときは今度は家族みんなで『大乱闘スマッシュブラザーズ』(マリオ含むオールスターキャラ乱闘ゲーム)なんてのも盛り上がりますね。
総合すると、「マリオカート/マリオパーティ → マリオUデラックス/マリオメーカー → ペーパーマリオ/ルイージマンション → マリオワンダー等最新作」という流れは、多くの初心者ファミリーにとって無理なくマリオシリーズを満喫できる黄金ルートと言えます。もちろん、お子さんの年齢や好みに応じて順番は前後させてOKです。例えば「うちはみんな運動好きだから最初からマリオテニスにしたい」でも良いでしょうし、「1人っ子なのでストーリー重視のペーパーマリオから親子でやってます」でも大丈夫です。
大切なのは、家族全員が楽しめること。どのゲームから始めても、親が一緒にプレイし、子どもの笑顔を引き出してあげれば、それが正解のルートです。最初の1本でマリオゲームの魅力に触れたら、あとは自然と「次はこれやってみたい!」と家族内で話が盛り上がることでしょう。ぜひ皆さんも、自分たちならではのマリオゲーム遍歴を作り上げてください。
まとめ
Nintendo Switchのマリオシリーズのゲームは、まさに家族で遊ぶのにうってつけの名作揃いです。未就学児から小学生、高校生になっても、大人になって親子が逆転しても、みんなで集まればいつでもマリオゲーム 子どもと遊ぶ時間に花が咲きます。
本記事では各ゲームの特徴や対象年齢、家族での楽しみ方のコツをたっぷりご紹介してきました。簡単に振り返ってみましょう。
- マリオカート8 デラックス:小さな子でもアシスト機能で楽しめ、レースで大盛り上がり。家族向けソフトの代表格。
- マリオパーティ シリーズ:ボードゲームとミニゲームで笑いが絶えない。兄弟や親子のコミュニケーションに最適。
- マリオテニス エース:体を動かすスイングモードで室内運動会! シンプルモードで初心者も安心。
- ペーパーマリオ オリガミキング:親子で物語を味わい、謎解きを協力。読み聞かせプレイもできるハートフルRPG。
- スーパーマリオブラザーズ ワンダー:最新の驚き満載2Dマリオ。4人協力プレイで家族みんなで冒険できる。
- New スーパーマリオブラザーズ U デラックス:初心者に優しいキャラで2Dマリオ入門。家族で協力してアクション上達も。
- スーパーマリオメーカー 2:コースを作って遊んで創造性爆発。家族内発表会で子どもの才能が開花するかも。
- ルイージマンション3:怖がりさんも勇気を出せるおばけ退治。親子協力で謎解き達成の喜びを共有。
それぞれのゲームに、それぞれの楽しさと学びがありました。年齢別のポイントや、オフラインプレイの良さ、ゲームを通じた子どもの成長、家庭イベントへの活用法、親がゲームを選ぶ際の留意点なども押さえ、準備は万端です。
あとは実際にNintendo Switchを手に取り、家族みんなでマリオの世界へ飛び込むだけ! 最初は親御さんも戸惑うかもしれませんが、子どもはすぐにコツを掴んで一緒に楽しめるようになります。ゲームの中で響く子どもの笑い声や、クリアしたときの「やったー!」という声、負けて悔しがる涙も、その全てが家族の思い出に刻まれます。そして何より、画面の前で肩を並べる時間そのものが、かけがえのない宝物になるでしょう。
最後に、この記事で取り上げた内容や**「Switch 家族向けソフト」**というキーワードが、ご家庭のゲーム選びの一助になれば幸いです。マリオシリーズは初心者ファミリーにこそ優しく、そして深く楽しませてくれる作品ばかり。ぜひ気になったゲームからチャレンジしてみてください。親子で、兄弟で、時には祖父母も交えて、マリオゲームが皆さんの笑顔を引き出してくれることを願っています。さあ、ゲームの世界で家族の冒険を始めましょう!
 | 迷ったらコレ!秋田駅の人気お土産17選 |
 | 木下大サーカス東京公演を子連れで楽しむ徹底ガイド |
 | 【2025年最新版】三重県のおすすめグランピングスポット4選!大自然で贅沢なひとときを満喫しよう |
 | 霧島でお土産を買うならココ!貰って嬉しいお土産9選 |
 | 大宮横丁は子連れ家族におすすめ!レトロで楽しいグルメスポット徹底ガイド |
