六道珍皇寺

六道珍皇寺の基本情報
【スポット】六道珍皇寺
【ふりがな】ろくどうちんのうじ
【 住所 】京都府京都市東山区大和大路通四条下る四丁目小松町595
【アクセス】京阪本線 清水五条駅 徒歩約10分
【最寄り駅】清水五条駅
【営業時間】9:00~16:00(受付終了15:45)
【 料金 】大人600円、中高生300円、小学生200円
【クーポン】公式ウェブサイトにて割引クーポンあり
六道珍皇寺
が含まれる観光マップ
あの世とこの世の境目!?六道珍皇寺の観光情報やアクセス方法まとめ
六道珍皇寺について
京都市は東山区に、六道珍皇寺、通称「六道さん」と呼ばれる、臨済宗建仁寺派の寺院があります。
この六道さんはちょっと不思議で、実しやかに「あの世とこの世の境目がある」とも囁かれているのです。
どうしてそのような噂があるのか、それは六道珍皇寺の付近は平安京の時代、火葬地であった鳥辺野に通ずる道筋にある事に関係しています。
昔々はこの地において遺骸を埋葬地、火葬場まで運び送る野辺の送りを行っていた事で、「人世の無常、儚さを感じる場所」だと言われるようになったのです。
六道とは仏教の教義で「地獄道」、「餓鬼道」、「畜生道」、「修羅(阿修羅)道」、「人道」、「天道」といった六つの冥界の事をいいます。
人間は亡くなった後も「因果応報」により六道を輪廻転生する、つまり生と死を繰り返しながら逆転しているといった教えがあります。
丁度、六道珍皇寺の境内の辺りが「六道の分岐点(あの世とこの世の接点)」であるとして、六道珍皇寺には冥界へ繋がる入口があるといわれているのです。
拝観時間
10:00~16:00
拝観料
600円
六道珍皇寺へのアクセス方法
バスでのアクセス
①JR京都駅から:市バス206番 東山通 北大路バスターミナル行→清水道バス停下車、徒歩約5分
②京阪電車清水五条駅から:市バス80番 祇園行→清水道バス停下車、徒歩約5分
③京阪電車祇園四条駅、または阪急電車河原町駅から:市バス207番 東福寺九条車庫行→清水道バス停下車、徒歩約5分
駐車場について
一応、六道珍皇寺専用駐車場はありますが、3台程しか駐車できないとても狭いスペースです。
周囲も道幅が狭い所がありますから、バスでのアクセスをおすすめします。
六道珍皇寺の見どころ
冥途通いの井戸と黄泉がえりの井戸
六道珍皇寺の境内には「冥途通いの井戸」と呼ばれる不思議な井戸があります。
そう呼ばれるようになったのは後に「閻魔大王に仕えた人物」といった話が残っている、小野篁が関係しているのです。
小野篁とは参議小野岑守の元に生まれた後、嵯峨天皇に仕えていたとされる、平安初期の官僚です。
学者や詩人、歌人として名が知られる程頭が良いだけではなく武芸にも大変秀でた人物でしたが、野狂と言われる程、奇行が多い人物でもありました。
そんな小野篁が何故閻魔大王に仕えるようになったのか、一説では「亡くなった母に会いたいがためにあの世とこの世を行き来していた」といわれています。
餓鬼道に堕ちてしまった母親を救う為に閻魔大王に交渉し、地獄の冥官となったのだそうです。
昼はこの世の朝廷で仕事をし、夜は井戸を通ってあの世へ行っている内に閻魔庁に勤めていたのでしょう。
本当にこちらとあちらを行き来していたのか、それとも小野篁自身の性格や振る舞いにより、そう噂されていたのかは定かではありません。
しかし江談抄や今昔物語にはそのような明記がある事からも、もしかしたら本当にあの世とこの世を往復していたのかもしれませんね。
小野篁がこの世からあの世へ行く際に使っていたとされるのが、境内にある「冥途通いの井戸」です。
そしてもう1つ、あの世からこの世へ戻る際に使用されていたのが「黄泉がえりの井戸」とされています。
黄泉がえりの井戸は、近年になって旧境内内地から発見されました。
ゆっくりと両方の井戸の中を覗いてみてください。
鉄格子がありますが、それでも吸い込まれそうな程、ちょっと不思議な雰囲気がある井戸です。
冥途に響くお迎え鐘
六道珍皇寺にはもう1つ、不思議な言い伝えがあります。
それは、冥途まで響くといわれる「お迎え鐘」です。
こちらの鐘は従来の鐘とは違い、何と四方を壁に囲まれた中にあります。
壁には穴が開いており、そこから伸びる紐を引いて鐘を鳴らすのですが、この鐘の音がお精霊(しょうらい)さんを迎える合図となるのだそうです。
そういった話が出てきたのは、ある由来からでした。
お迎え鐘は六道珍皇寺の開基である慶俊僧都が造らせたとされるますが、ある時に僧都が唐国へ向かう事になりました。
その際「この鐘を3年間、土の中に埋めておくように」と言い残して旅立ったのです。
しかし留守を任された寺僧は待ちきれなくて1年半経った頃に地中から掘り出し、鐘をついてしまいました。
すると唐国にいた僧都の元へも聞こえたとの事です。
僧都はというと「3年地中に埋めておいたなら後は何もせずとも6時に知らせてくれるようになったはずが」と残念がったといいます。
こうした話が今昔物語等にあった事から「そんなに遠くまで聞こえるならば、冥途にも聞こえるだろう」といわれるようになったのでした。
十万億土の冥界へまで届いてしまう鐘の音色、そう聞くとちょっと恐ろしいですが、六道珍皇寺で行われる六道まいりには欠かせない鐘です。
閻魔像や地獄の絵図(要予約)
境内には閻魔像と小野篁像の他、地蔵と地獄絵図もあります。
ちょっと怖い絵ですが、迫力たっぷりなので是非一度は目にしてください。
六道まいり
京都では、毎年8月13~16日の五山の送り火で終わる盂蘭盆(うらぼん)では、先祖の霊を祀る風習があります。
その盂蘭盆の前、8月7~10日までの間に精霊、つまり御魂(みたま)、亡くなった人の魂を迎える為に六道珍皇寺へ参拝するのです。
この習わしを「六道まいり」、もしくは「お精霊さん迎え」と呼んでいます。
どうしてこのような風習ができたのか、それは六道珍皇寺の周辺は昔、墓所である鳥辺山の麓、東の葬送地だったからです。
その為に六道珍皇寺にはあの世とこの世の境目があり、そこにお精霊さんが集まるとされています。
六道まいりを行うにはまず境内の山門にある花屋で高野槇(こうやまき)を購入します。
これは、お精霊さんが高野槇の枝に乗り、こちらへ帰ってくるからです。
そして本堂前で水塔婆(みずとうば)にお精霊さんの戒名を書いてもらい、順番に迎え鐘を鳴らしていきます。
その後は水塔婆を線香で浄め、地蔵尊宝前で高野槙でもって水塔婆を水回向して終わりです。
京都で暮らす人々はこうした風習を大切にしており、今も尚、続いているのです。
六道珍皇寺での注意点
井戸を近くで撮影しない事
六道珍皇寺にある冥途通いの井戸と黄泉がえりの井戸ですが、この井戸を近くで撮影してはいけないと言われています。
もしも近くで撮影すると「いけないものが写ってしまう」らしく、必ず遠くから撮影しなければいけません。
何が写るのが怖くて撮影は出来ませんでしたが、近づいてみると夏でもひんやりしている場所です。
野辺送りの土地でもありますから、この世のものではないものが写り込んでしまうのかもしれませんね。
特別公開の日に行く事
特別拝観日が年に何回かあります。
例えば冬の特別寺宝展だったら冥土通いの井戸と黄泉がえりの井戸の他、法橋院達作の小野篁像等が拝観できるのです。
そういった「普段は見る事のできないものが見れる日」に行く方が、色々な珍しい物を見れておすすめです。
特に冥土通いの井戸と黄泉がえりの井戸を目当てに行く場合は、通常時は格子窓の奥からしか眺められない為、特別公開の日に行きましょう。
普段は近づけない井戸に近づけ、水占いもできるのです。
ただし、観光客がとても多い場所でもあるので混雑には要注意です。
六道珍皇寺周辺観光スポット
みなとや幽霊子育て飴本舗
その昔、母親の幽霊が我が子の為に夜な夜な飴を買いに行きました。
店主は不思議に思いつつも飴を売っていたある日、子供の泣き声が聞こえたのです。
慌てて泣き声の聞こえる所を掘り返してみると、そこには毎晩飴を買いにきていた女性の死体と、生きている赤ん坊がおりました。
どうやら母親は亡くなった後も子供が心配で、飴を与える為に毎夜買いに出ていたのです。
その飴屋こそがみなとや幽霊子育て飴本舗だともいわれており、こちらでは幽霊子育飴を購入する事ができます。
飴は黄金色でちょっと変わっており、でも甘すぎず美味しいです。
話しのネタに、一つお土産に買って帰ってもいいですね。
鍵善 良房本店
六道珍皇寺から徒歩約10分程の所にある鍵善さんでは、吉野葛を100%使用した、美味しいくずきりを頂けます。
本場のくずきりのお店としても有名で、店内は雰囲気が良く、落ち着く造りとなっています。
くずきりの他には水ようかん等のお菓子も置いてありますから、和菓子好きにはおすすめです。
不思議な雰囲気漂う六道珍皇寺へ出掛けましょう
昔は野辺送りがあった場所であり、あの世とこの世の境目だなんて聞くと怖い気もしますが、一度は行ってみてほしい寺院です。
六道珍皇寺の周辺には様々な寺院や観光スポットがありますから、京都旅行の際には是非お立ち寄りください。
ただし夕方、逢魔時にはご注意ください、もしかするとあの世の見えざるものが見えてしまうかもしれませんよ。
[wdi_feed id=”730″]
京都のスポットを
ジャンルから探す
おすすめ記事



もっと写真を見る
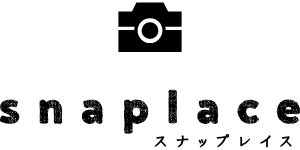 日本最大級のSNS映え観光情報サービス。SNSの様々なデータを分析し、インスタ映え、ツイッター映え、定番スポットを地図上に表示。大手旅行会社である日本旅行やH.I.S.とも協業し、フォトジェニックスポットマップも提供。観光ガイドでは紹介されない、知る人ぞ知るニッチなスポットもカンタンに探せ、各スポットの特徴が3秒で分かる。
日本最大級のSNS映え観光情報サービス。SNSの様々なデータを分析し、インスタ映え、ツイッター映え、定番スポットを地図上に表示。大手旅行会社である日本旅行やH.I.S.とも協業し、フォトジェニックスポットマップも提供。観光ガイドでは紹介されない、知る人ぞ知るニッチなスポットもカンタンに探せ、各スポットの特徴が3秒で分かる。














